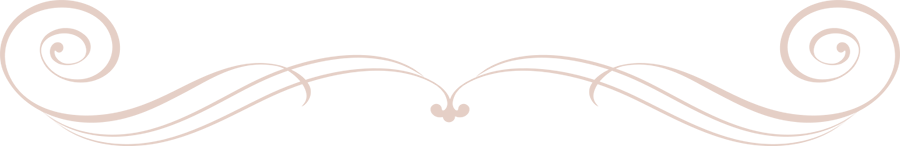
 尾張徳川家初代当主の徳川義直(源敬・家康9男)の出生から歿後の四十九日までの尾張家の公式記録です。昨年刊行した第一に引き続き、第二は寛永8年(1631)正月から同16年(1639)12月までを収録しました。義直32歳より40歳までの年代記です。
本巻には、二代将軍・大御所となった兄秀忠の死、甥に当たる駿河大納言忠長の改易事件、さらに三代将軍家光の病気の記事など、将軍家に関わる重要記事とともに、正室春姫(高原院)の江戸下向とその死去・葬礼、嫡男光友と千代姫(家光長女)の婚礼など、尾張家と将軍家との関係が具体的にわかる記事が多く記載されています。儒教を尊崇し、学問を好んだ義直の人となりや人間関係も、記事からうかがえます。
江戸初期の幕政や藩政、思想・学問環境など、さまざまな切り口で読むことができる記録です。ふるってご活用下さい。
尾張徳川家初代当主の徳川義直(源敬・家康9男)の出生から歿後の四十九日までの尾張家の公式記録です。昨年刊行した第一に引き続き、第二は寛永8年(1631)正月から同16年(1639)12月までを収録しました。義直32歳より40歳までの年代記です。
本巻には、二代将軍・大御所となった兄秀忠の死、甥に当たる駿河大納言忠長の改易事件、さらに三代将軍家光の病気の記事など、将軍家に関わる重要記事とともに、正室春姫(高原院)の江戸下向とその死去・葬礼、嫡男光友と千代姫(家光長女)の婚礼など、尾張家と将軍家との関係が具体的にわかる記事が多く記載されています。儒教を尊崇し、学問を好んだ義直の人となりや人間関係も、記事からうかがえます。
江戸初期の幕政や藩政、思想・学問環境など、さまざまな切り口で読むことができる記録です。ふるってご活用下さい。
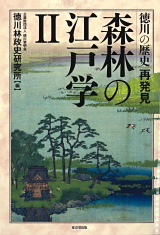 はしがき
総説 “暮らしを守る森林”-江戸時代からのメッセージ-
1 “暮らしを守る森林”へのまなざし
2 国土の変貌と水土保全への着目
3 列島を襲う風・飛砂・潮と“緑の屏風”
4 災害からの復旧・復興と森林への期待
5 “暮らしを守る森林”と近代林政
はしがき
総説 “暮らしを守る森林”-江戸時代からのメッセージ-
1 “暮らしを守る森林”へのまなざし
2 国土の変貌と水土保全への着目
3 列島を襲う風・飛砂・潮と“緑の屏風”
4 災害からの復旧・復興と森林への期待
5 “暮らしを守る森林”と近代林政
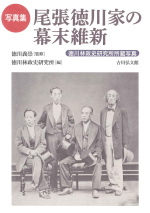 当研究所が所蔵する古写真のうち、尾張徳川家14代(のち17代)当主であった徳川慶勝が撮影した写真や、慶勝が歩んだ激動の幕末維新の時代を記録した写真307点を厳選掲載した写真集です。
初公開の写真も多数収録し、慶勝お手許の写真研究書・技術書も翻刻掲載しました。
はじめに(徳川義崇)
当研究所が所蔵する古写真のうち、尾張徳川家14代(のち17代)当主であった徳川慶勝が撮影した写真や、慶勝が歩んだ激動の幕末維新の時代を記録した写真307点を厳選掲載した写真集です。
初公開の写真も多数収録し、慶勝お手許の写真研究書・技術書も翻刻掲載しました。
はじめに(徳川義崇) 「国際森林年」であった2011年より当研究所で執筆・編集に着手した“江戸時代の林政史”の一般向け概説書です。
「概説編」と「基礎知識編」の2部構成で、概説編は「森林政策から見た“徳川三百年”」と題し、戦国末から明治初め頃までの森林政策の流れを概観しています。基礎知識編は、江戸時代の森林を知る上で必要な事項を48項目選んで、それぞれに解説を施しました。
〔概説編〕森林政策から見た“徳川三百年”
1 森林荒廃をもたらしたもの
「国際森林年」であった2011年より当研究所で執筆・編集に着手した“江戸時代の林政史”の一般向け概説書です。
「概説編」と「基礎知識編」の2部構成で、概説編は「森林政策から見た“徳川三百年”」と題し、戦国末から明治初め頃までの森林政策の流れを概観しています。基礎知識編は、江戸時代の森林を知る上で必要な事項を48項目選んで、それぞれに解説を施しました。
〔概説編〕森林政策から見た“徳川三百年”
1 森林荒廃をもたらしたもの |
◎家康・秀忠・家光ISBN978-4-490-20786-6 C1021 本体2400円+税〔総説〕:徳川の世の幕開け〔竹内 誠〕徳川家康の遺訓〔竹内 誠〕 二代将軍秀忠の人物像〔太田尚宏〕 「寛永小説」に見る三代将軍家光〔深井雅海〕 徳川御三家の創出と将軍家〔白根孝胤〕 |
 |
◎元禄時代ISBN4-490-20465-5 C1021 本体2400円+税〔総説〕:元禄時代とは何か〔竹内 誠〕元禄の武士〔竹内 誠〕 生類憐み令と元禄政治〔深井雅海〕 将軍綱吉の御成〔須田 肇〕 元禄時代の江戸みやげ話〔太田尚宏〕 |
 |
◎享保の改革ISBN4-490-20524-4 C1021 本体1900円+税〔総説〕:八代将軍徳川吉宗と享保の改革〔竹内 誠〕享保の改革と江戸〔竹内 誠〕 享保の渡来象始末記〔太田尚宏〕 徳川宗春の実像と治政〔白根孝胤〕 御庭番の隠密活動〔深井雅海〕 |
 |
◎田沼時代ISBN4-490-20552-X C1021 本体2200円+税〔総説〕:田沼意次とその時代〔竹内 誠〕田沼意次の権勢と失脚〔竹内 誠〕 田沼意次の出頭〔深井雅海〕 田沼意知刺殺事件の真相〔白根孝胤〕 随筆に見る江戸の風俗〔太田尚宏〕 |
 |
◎寛政の改革ISBN4-490-20590-2 C1021 本体2300円+税〔総説〕:松平定信と寛政の改革〔竹内 誠〕天明の打ちこわしと寛政の改革〔竹内 誠〕 松平定信政権成立の裏事情〔深井雅海〕 御三家の系譜編さん事業〔白根孝胤〕 御代官所の構造改革〔太田尚宏〕 |
 |
◎文化・文政の世ISBN978-4-490-20611-1 C1021 本体2300円+税〔総説〕:11代将軍家斉とその時代〔竹内 誠〕化政期の江戸社会〔竹内 誠〕 将軍家斉の官位昇進儀礼〔深井雅海〕 尾張藩の代替わりと押し付け養子〔白根孝胤〕 将軍の鯛と御用魚問屋〔太田尚宏〕 |
 |
◎天保の改革ISBN978-4-490-20637-1 C1021 本体2400円+税〔総説〕:水野忠邦と天保の改革〔竹内 誠〕老中水野忠邦と名町奉行遠山金四郎〔竹内 誠〕 天保の日光社参〔深井雅海〕 諸国巡見使と領民〔白根孝胤〕 天保の人返し政策〔太田尚宏〕 |
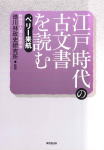 |
◎ペリー来航ISBN978-4-490-20668-5 C1021 本体2400円+税〔総説〕:ペリー来航とその時代〔竹内 誠〕使節ペリーへの贈答品と相撲取〔太田尚宏〕 黒船来航と雄藩大名〔白根孝胤〕 安政の列島大激震〔太田尚宏〕 桜田門外の変と御庭番〔深井雅海〕 |
 |
◎幕末の動乱ISBN978-4-490-20704-0 C1021 本体2400円+税〔総説〕:幕末動乱の時代〔太田尚宏〕文久の幕政改革〔深井雅海〕 将軍上洛と徳川慶勝〔白根孝胤〕 第一次長州征討をめぐる人間模様〔竹内 誠〕 将軍不在の江戸〔太田尚宏〕 |
 |
◎徳川の明治維新ISBN978-4-490-20737-8 C1021 本体2400円+税〔総説〕:江戸から明治へ〔竹内 誠〕江戸城請取りの顛末〔深井雅海〕 旧幕臣の駿河移住〔藤田英昭〕 徳川慶勝が見た宮中社会〔白根孝胤〕 森林をめぐる明治維新〔太田尚宏〕 |
徳川林政史研究所が平成30年度(2018)より取り組んでいる岐阜県中津川市加子母地区における史料調査の研究成果を、尾張藩の森林政策や山村の生活文化などのテーマに分けてわかりやすく紹介したブックレットシリーズです。今後も刊行の継続を予定しています。 非売品・残部僅少のため、ブックレット全文のPDFをこちらで公開しております。ブックレット本体の入手をご希望の方は別途当研究所へお電話・メール(rinsei@tokugawa.or.jp)などで事前にお問い合わせください。在庫を確認のうえ、追って発送手続等についてお知らせいたします。
第1巻 御山守の仕事と森林コントロール(芳賀和樹) |
|
A5判並製 ISBN 978-4-88604-036-7 令和2年刊行はじめに1 内木家文書からみた御山守の仕事 2 木口印入による森林コントロール 3 樹木の育成テストと種子・苗木の供給 4 御山の利用と跡地での植林 おわりに 全文PDF |
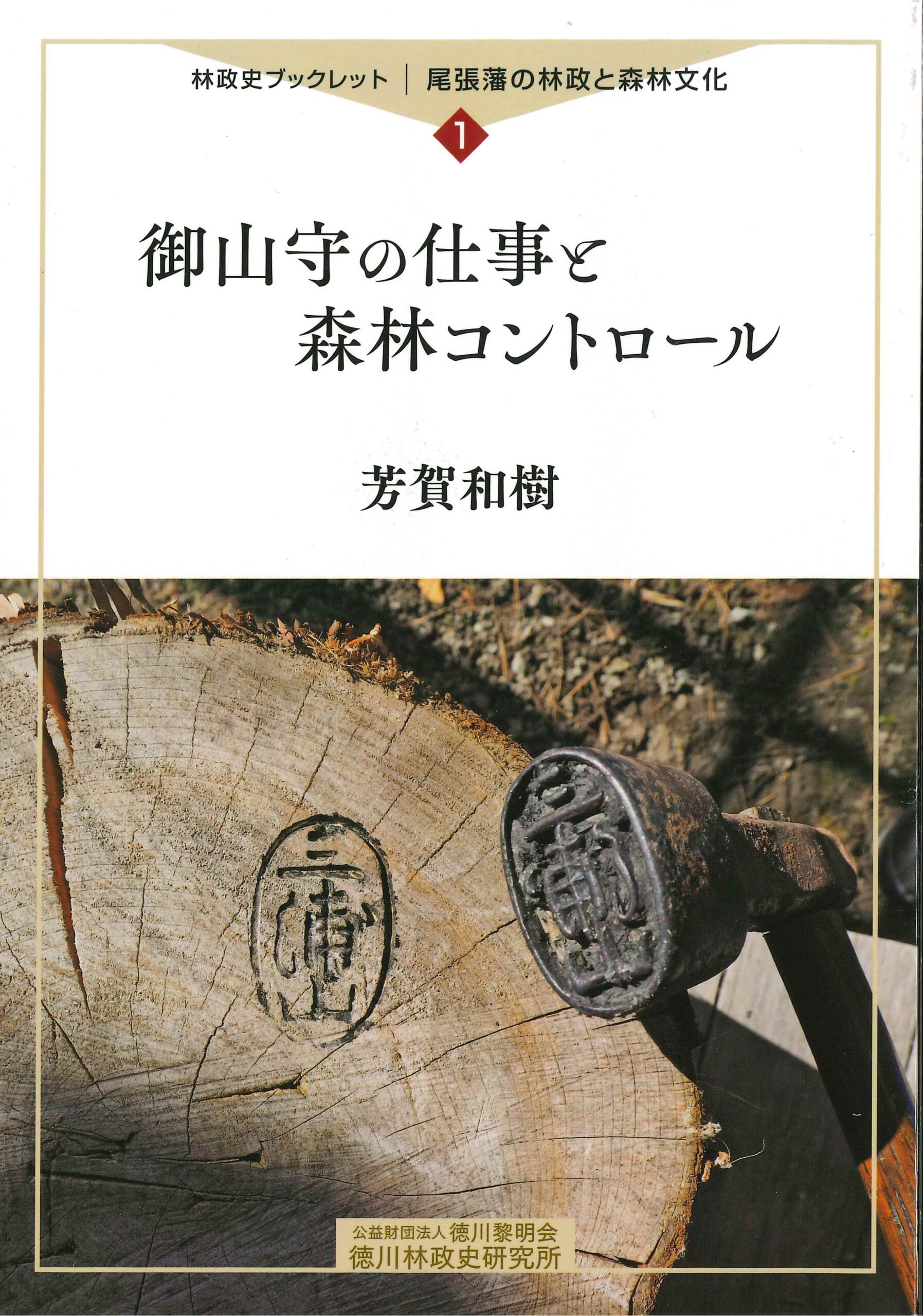 |
第2巻 山村の人・家・つきあい-江戸時代の“かしも生活”①-(太田尚宏) |
|
A5判並製 ISBN 978-4-88604-037-4 令和2年刊行プロローグ-“かしも生活”の舞台1 彦七の家族と「一家中」 2 暮らしを支え合う近隣・親類 3 暮らしの中の楽しみ あとがき-話は尽きねど- 全文PDF |
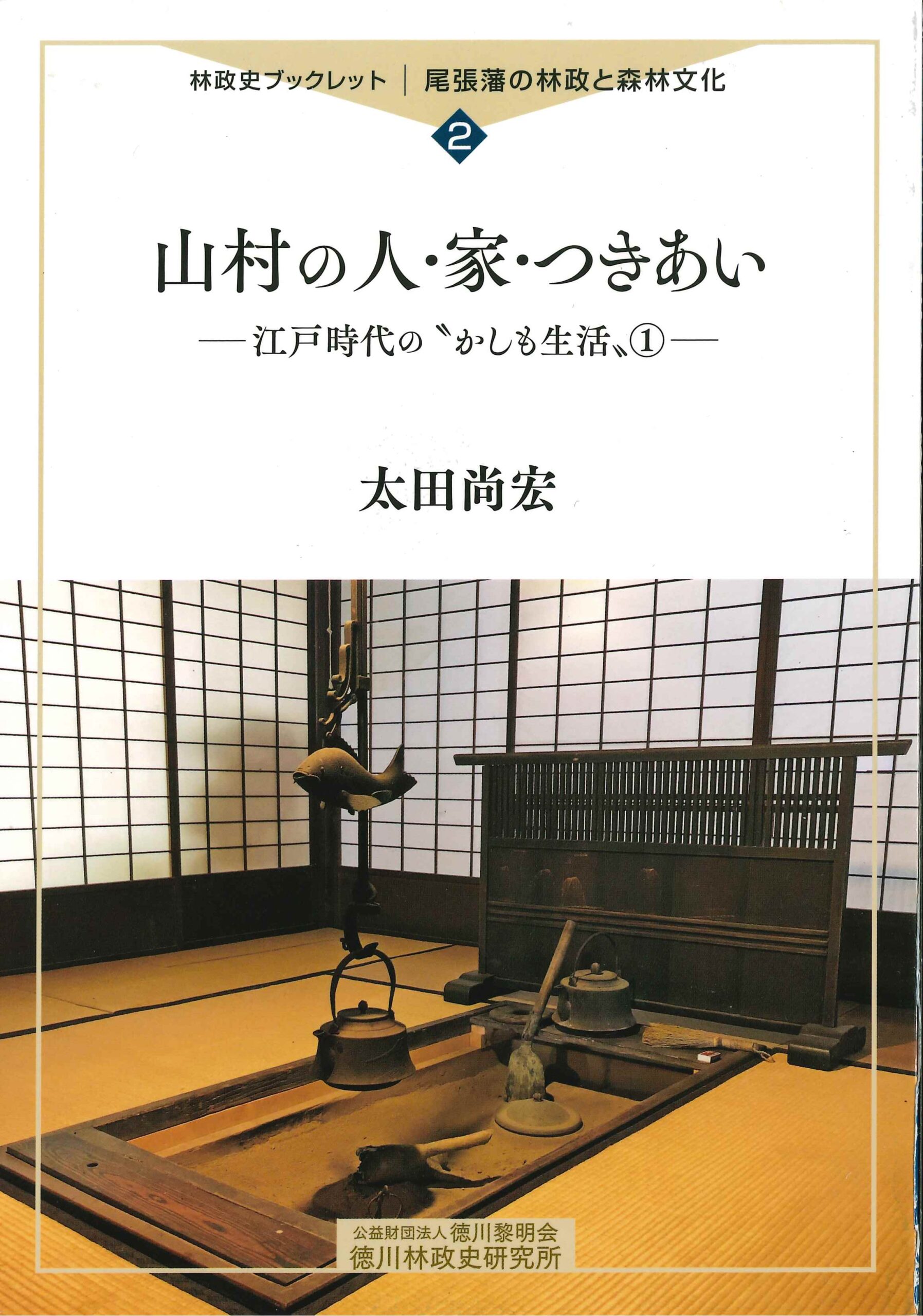 |
第3巻 尾張藩林政のなかの御山守(田原昇・芳賀和樹) |
|
A5判並製 ISBN 978-4-88604-038-1 令和3年刊行プロローグ1 御山守前史~内木家の出自と御用~ 2 内木家の御山守就任と林政改革 3 木曽材木方の組織と御山守の仕事 4 手代格への昇進運動と近親者の山手代就任 エピローグ 全文PDF |
 |
第4巻 四季折々の暮らしと文化-江戸時代の“かしも生活”②-(仲泉剛・萱場真仁) |
|
A5判並製 ISBN 978-4-88604-039-8 令和3年刊行はじめに1 四季折々の暮らしと文化 2 農事にみる暮らし 3 食べものにみる加子母の四季と日常 おわりに 全文PDF 付録PDF |
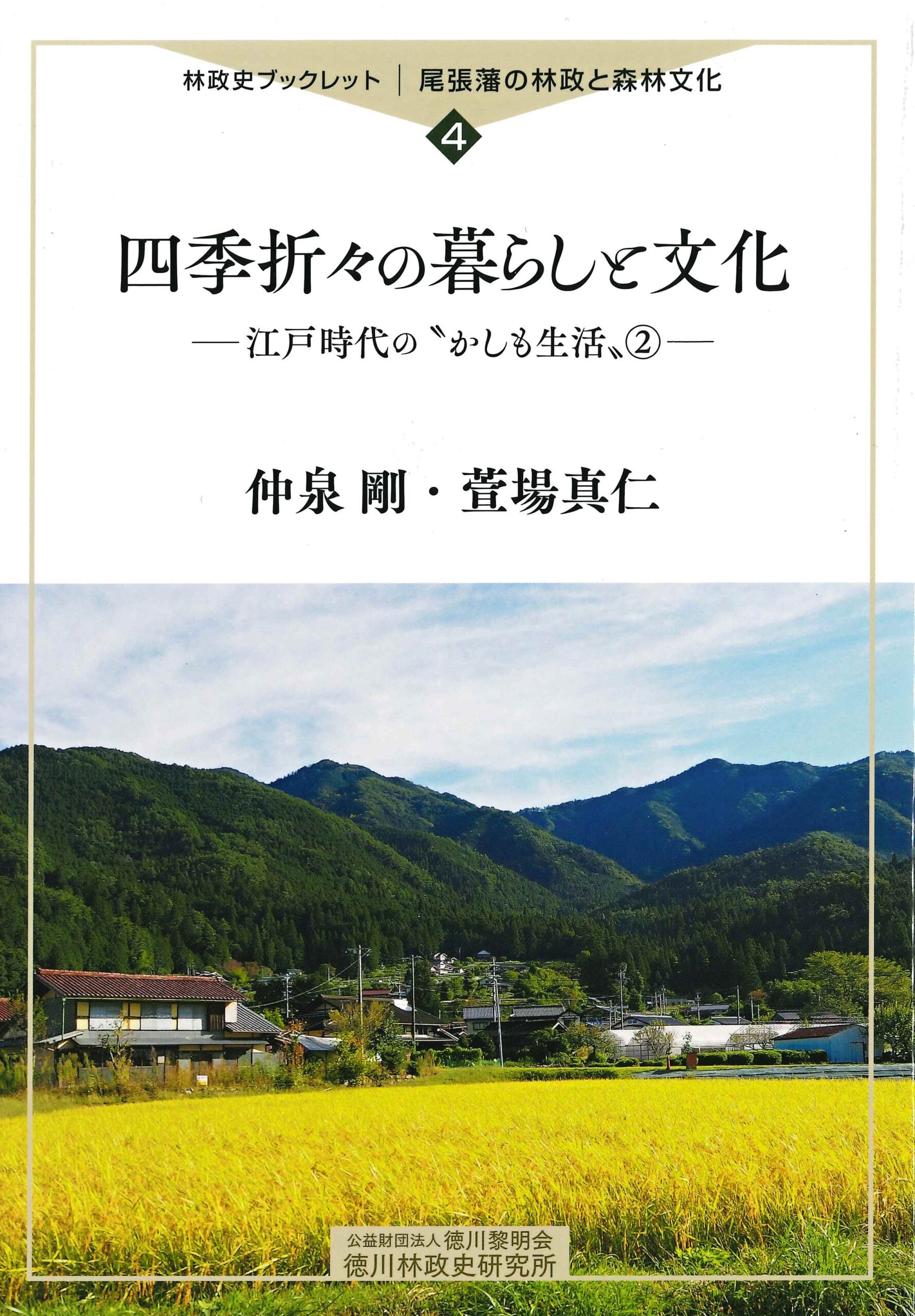 |
第5巻 森林利用の秩序と御山守・村(栗原健一・髙木謙一) |
|
A5判並製 ISBN 978-4-88604-040-4 令和4年刊行プロローグ1 三浦山・三ヶ村御山見廻り 2 盗伐をめぐる御山守・村 3 村方と御停止木 4 家作見分と村方 エピローグ 全文PDF |
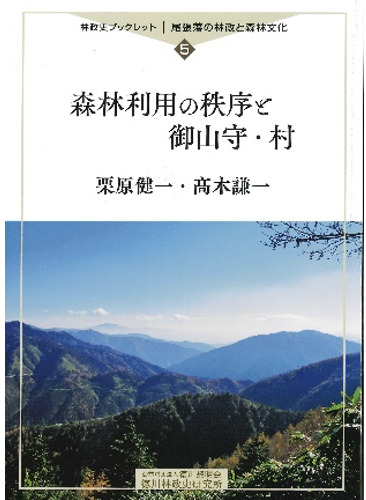 |
第6巻 自然の脅威と樹木の活用(淺井良亮・萱場真仁) |
|
A5判並製 ISBN 978-4-88604-042-8 令和5年刊行プロローグ1 加子母の気候と自然災害 2 枯損木の活用と御山守 3 村々における樹木の活用 エピローグ 全文PDF |
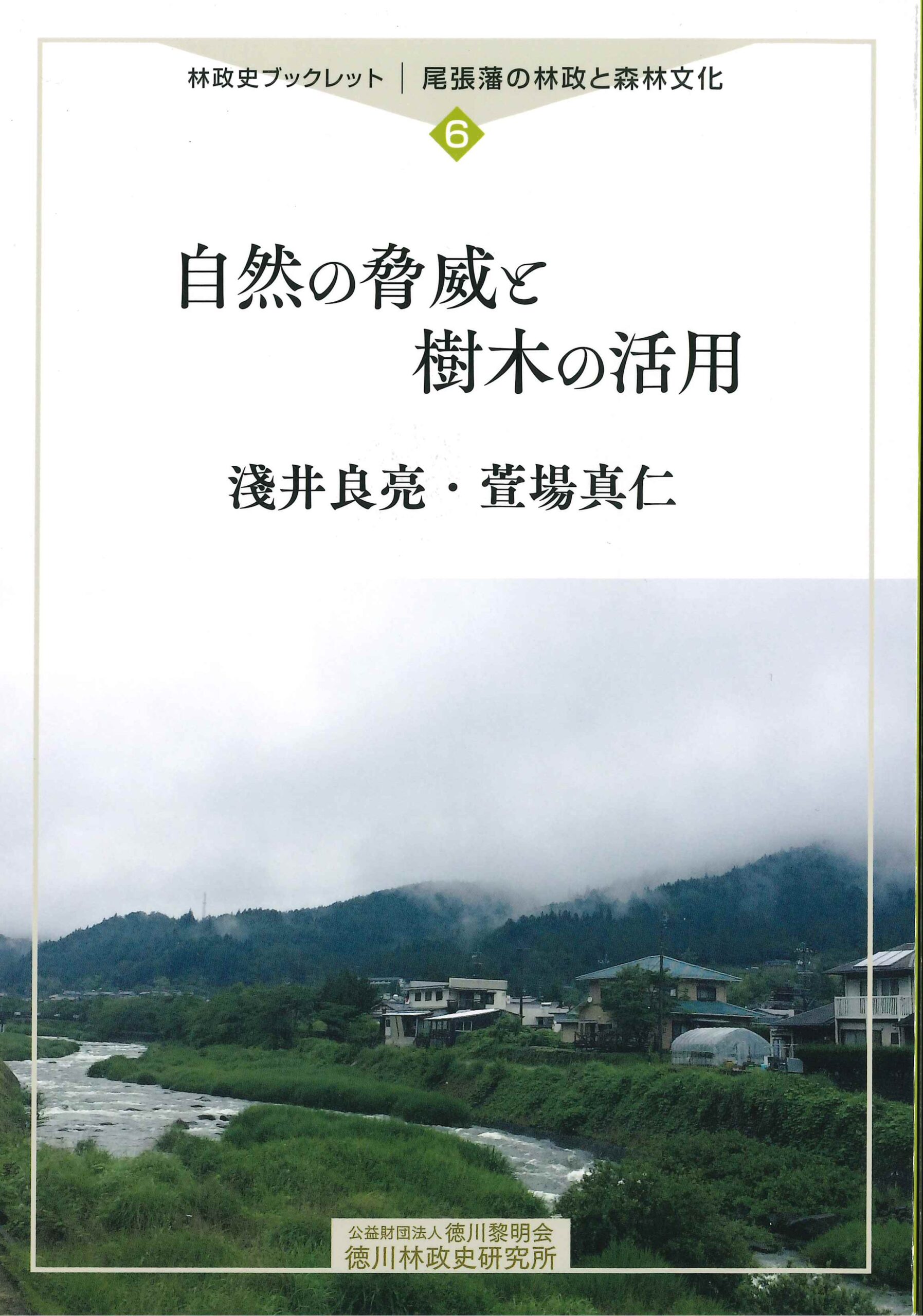 |
第7巻 子どもから大人へ-江戸時代の“かしも生活”③-(髙木まどか・萱田寛也) |
|
A5判並製 ISBN 978-4-88604-043-5 令和5年刊行1 子どもの誕生と成長2 子どもの毎日 3 娘の嫁入り 4 加子母村の家族の姿 5 病に対処する 6 家族の「死」と向き合う おわりに 全文PDF |
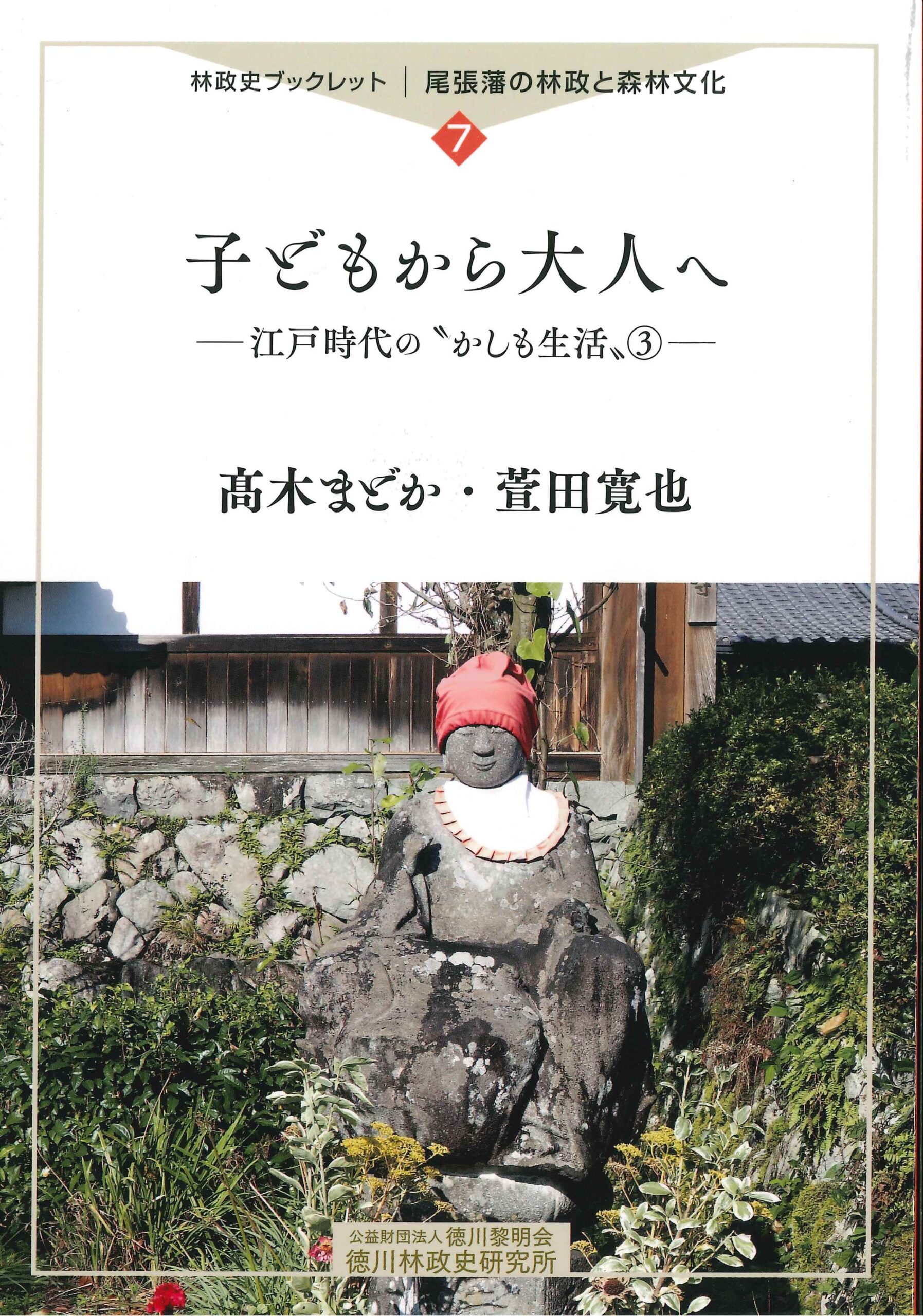 |
第8巻 明治維新と加子母の森林(太田尚宏・芳賀和樹) |
|
A5判並製 ISBN 978-4-88604-048-0 令和6年刊行プロローグ-廃藩置県と森林の所属1 三浦山をめぐる明治維新 2 森林の官民有区分と歎願運動・村方騒動 3 近代の森林管理秩序の形成 エピローグ-混乱から新たな秩序へ 全文PDF |
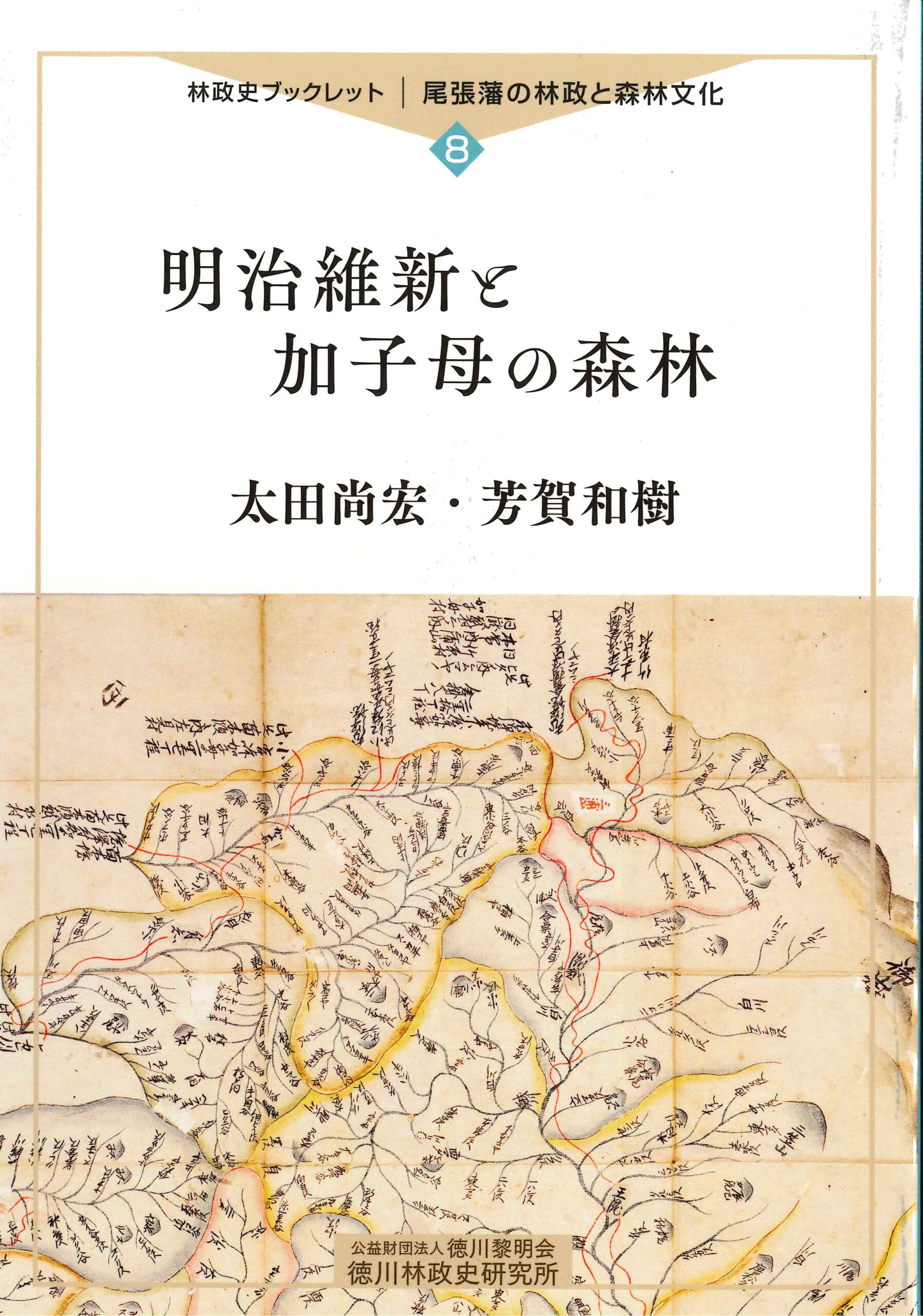 |
第9巻 人・物・お金にみる山村の暮らし-江戸時代の“かしも生活”④- (仲泉剛・林幸太郎) |
|
A5判並製 ISBN 978-4-88604-049-7 令和6年刊行はじめに 1 暮らしを支えるお金と物2 村のなかの商人・職人 3 村に流入するお金 4 村外からやってくる商人・職人 5 つながる内と外 おわりに 全文PDF |
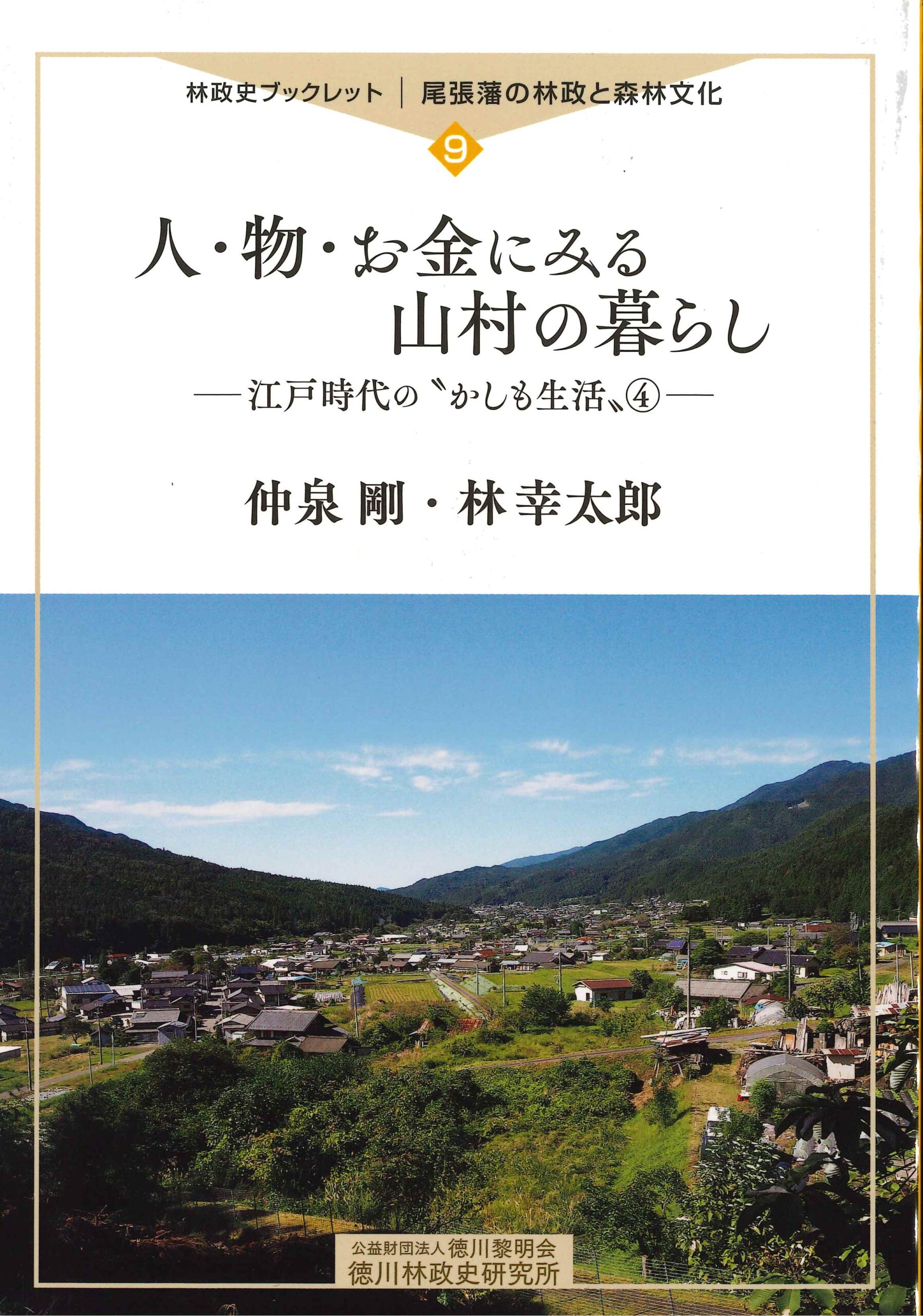 |
第10巻 木材生産を支える人びと (萱場真仁) |
|
A5判並製 ISBN 978-4-88604-051-0 令和7年刊行プロローグ1 木材の伐採と搬出 2 木材生産に携わる人びと 3 御山守内木家と杣頭たち エピローグ 全文PDF |
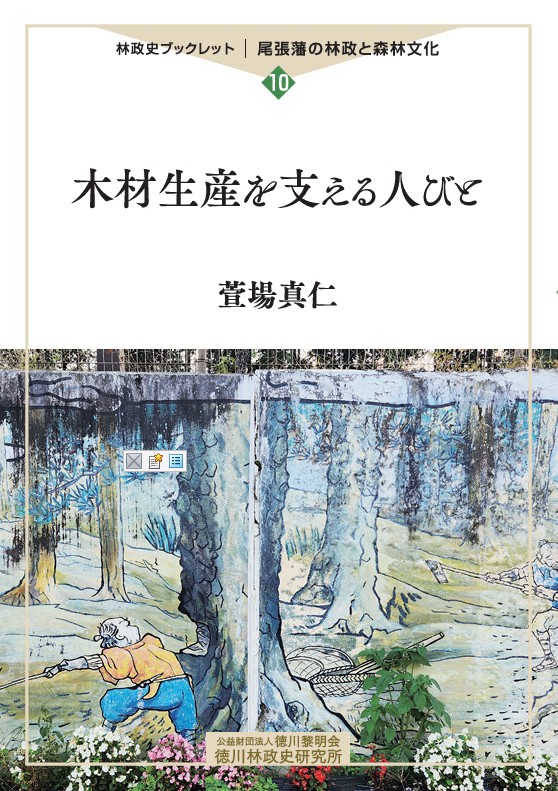 |
第11巻 加子母村の朝・昼・夜-江戸時代の“かしも生活”⑤- (髙木まどか) |
|
A5判並製 ISBN 978-4-88604-052-7 令和7年刊行はじめに1 内木家の毎日 2 季節を過ごす 3 変わっていく日常 おわりに 全文PDF |
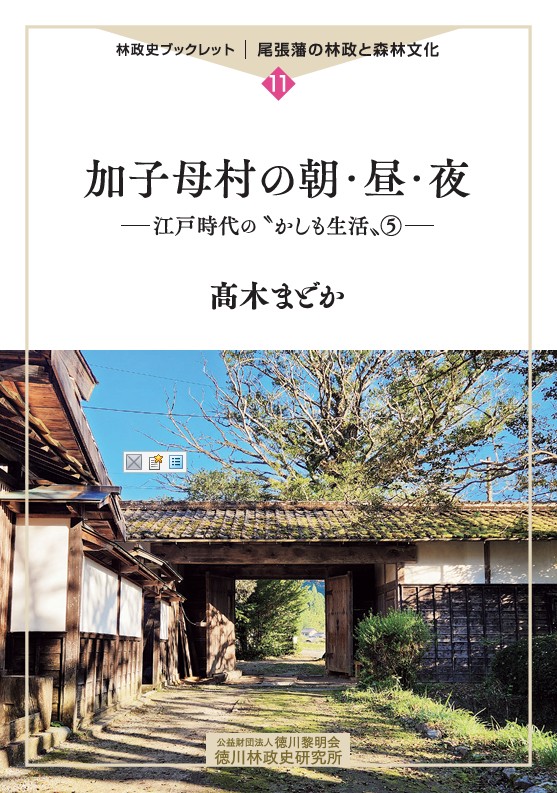 |
閲覧日:
火曜日・水曜日10:00~16:30
*閲覧をご希望の場合は、事前に申請が必要です。
閲覧申請はこちら
*休日・祝日および、8/10~8/20、12/20~1/10、3/20~4/10は閲覧を休止します。