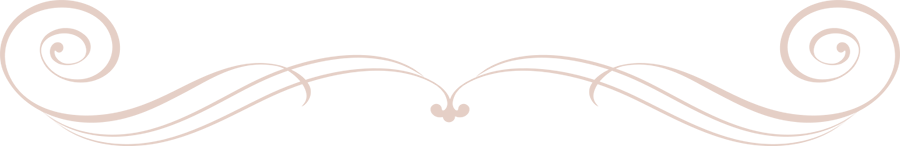
江戸時代以前の森林利用は、天然林の伐採がほとんどで、一部で植林が奨励されることはあっても、長期的な計画に基づく森林の保続策というべき内容ではなく、人工林の育成というには程遠いものでした。いわば山々に自生する樹木を選んで伐るだけの〝採取林業〟の時代だったのです。 奈良・平安・鎌倉の各時代には、宮殿・政庁・寺院などの造営材となるべき大材・良材を求めて、まず政権所在地に近接する国々の山から伐り出しが行われ、そこで大材・良材の確保が困難になると、次第に伐採する地域を外縁部へと広げていくという方法がとられました。畿内近国から始まった用材の伐り出しは、紀伊・美濃・信濃などへと拡大し、鎌倉政権期には伊豆・駿河・遠江などへと広まりました。こうして戦国時代の末期までには、大和・近江・伊賀を中心とした畿内地方と、これに隣接する中国地方の東部、中部地方、関東地方の西部、四国地方の内海寄りの地域で領主による用材生産が盛んに行われるようになったといわれます。 戦国の争乱を経て、織田信長・豊臣秀吉により全国が平定されると、統一政権の実力を誇示するような巨大城郭が次々と建設されました。ことに豊臣秀吉は、城郭の建設や修築、寺院の建立に熱心で、天正11年(1583)には大坂城の修築を開始、関白となった翌年の同14年には聚楽第や方広寺大仏殿の建設のため、諸国にその用材確保を命じました。 このうち方広寺大仏殿の建設にあたっては、秀吉は配下の奉行や大工らを全国の著名な林業地帯へと派遣し、九州・四国・中国諸国や信濃(木曽)・紀伊(熊野)などを用材伐り出しの有力候補地としました。そして、これらの地を所領とする諸将に対して出材を命じ、九州では大友・立花・島津、四国では藤堂・蜂須賀・長宗我部、中国では毛利・小早川・吉川の各氏が大材の伐り出しを実施しています。また、熊野・吉野・木曽・飛驒などの地域へは、美濃・近江の大名や直属の奉行らを派遣して出材を担当させました。 さらに秀吉は、東北地方の森林地帯へも触手を伸ばしました。秀吉は文禄2年(1593)、米代川流域に豊富なスギの天然林を有する能代(秋田県)の秋田実季に対して、大船1艘分の大割板の運上を命じ、加えて同じ頃に淀船30艘分の材木を供出するよう指示しました。また、同4年から慶長4年(1599)までは伏見城の普請用としてスギ板の上納を命じましたが、このときのスギ板は、長さが6尺6寸~2間2尺5寸(約198~255センチ)、幅が1尺6寸~1尺9寸(約48~57センチ)、厚さが4寸5分~6寸(約13・5~18センチ)という大板で、これを年間750枚も供出するというものでした。このときの出材では、秋田氏のみならず、津軽氏・小野寺氏・戸沢氏などの諸大名も動員され、短期間に大量のスギの立木が伐り出されたといわれます。 このように秀吉は、全国統一をなし得たことを背景に、東北から九州に至る全国各地の森林に目を向け、城郭建築や寺院建立の名目で大量に用材を伐り出させ、森林を木材資源の供給源として積極的に利用する道筋を開きました。こうした過程で出材を経験した大名の中には、秀吉の命による運上が終わった後にも、自身の領国経営のために森林の伐採を続けた者もおり、秀吉による用材供出策は、全国の森林を供用林(経済林)として開発していく起爆剤となったといえるでしょう。 また、この出材事業による需要を契機に、森林伐採の先進地帯であった畿内近国の杣たちが、出羽・阿波・土佐さらには信州木曽など、全国各地へと移り住んでいったとされることも重要です。これにより斧を用いた伐倒や、川の流れを利用した運材などの技術が伝播し、木材生産が一層加速されていったものと思われます。 〔太田尚宏〕 参考文献 ▽所三男「林業」(地方史研究協議会編『日本産業史大系1 総論篇』、東京大学出版会、1961年) ▽脇野博「秋田藩林政と森林資源保続の限界」(徳川林政史研究所『研究紀要』43、2009年) ▽国土緑化推進機構企画・監修『総合年表 日本の森と木と人の歴史』(日本林業調査会、1997年)
慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、秀吉の蔵入地(直轄領)であった信州伊那・木曽などの森林を掌中に収め、これらを引き続き用材の生産拠点としました。 慶長8年に徳川幕府が開かれ、同11年に江戸城の修築が開始されたのを端緒として、この時期には未曽有の建設ブームがわき起こりました。駿府城・名古屋城をはじめとして、全国各地で城郭建築が相次ぎ、これにともない武家屋敷・寺社・町家などの城下町建設や交通路の整備といった土木工事も盛んに行われるようになって、建築・土木用材としての木材需要はうなぎ上りに膨れあがっていきました。 江戸城・駿府城・名古屋城の建築用材には、伊那・木曽の山々から伐り出された木材が大量に利用されました。 伊那地方では、主としてサワラの原木から割り取った榑木や板子という小型の用材が盛んに生産・搬出されています。榑木は、太い丸木を芯の部分から四つまたは六つ・八つに蜜柑のように割り取り、芯の近くと外側の部分を平らに削って木口を台形にしたものです。板子は、宍料・瓦木などとも呼ばれ、丸木の芯を避けて割り取り、木口を長方形に造材した厚板で、床板や天井板・壁板、建具の材料などに用いられました。伊那代官の千村平右衛門(「山村甚兵衛と千村平右衛門」参照)は、地付きの代官たちとともに村方を指揮して、これらの用材をおそらくは数十万挺という単位で生産し、天竜川の流れを利用して川下げし、江戸や駿府へと搬送したと思われます。 木曽での城郭用材伐り出しは、さらに多量なものでした。「木曽勘定書」という史料によれば、慶長11年に木曽代官の山村甚兵衛(「山村甚兵衛と千村平右衛門」参照)が担当した伐り出し材の数は、榑木が30万2200挺、瓦木が4万7600挺、土居(榑木の大型のもの)1万700駄などのほか、駿府築城用材として6寸~1尺角(1辺が約18~30センチ)で長さ2~3間(約3・6~5・4メートル)のヒノキの角材が6940本、サワラの大板が2000枚、木具柾(木具用の柾目に木取りした白木)が2000挺ほどであったといわれます。なお、駿府築城用材の伐り出しは翌年と翌々年にも続いたので、伐り出された総数は、少なくとも右の2~3倍程度に達するものと思われます。 さらに慶長15年になると、今度は名古屋築城用材の伐り出しが進められ、この年に山村甚兵衛より惣奉行の小堀遠州へ引き渡された用材の数は、3万7974本におよびました。ちなみに、この頃の木曽地方における用材伐り出しは、林業の先進地帯であった紀伊や伊賀から杣(伐木・造材を担当)・日用(運材を担当)を雇い入れるとともに、美濃・木曽・伊那などから集められた役人足を使って行われたといいます。 こうした築城用材の調達は、家康が直轄支配する森林からだけではありませんでした。関ヶ原の戦い後、長宗我部氏に代わって土佐国に入部した山内氏は、慶長12年の駿府城建設にあたり、用材として材木1万本を献納しています。しかし、同年12月に起きた火災でこれらの一部が焼失したため、山内氏は翌年4月に材木500本、8月には700本を追加献納しました。このような諸将からの献納木を含めれば、築城用材はきわめて膨大な数に達したであろうと推測されます。 〔太田尚宏〕 参考文献 ▽平尾道雄『土佐藩林業経済史』(高知市立市民図書館、1956年) ▽所三男『近世林業史の研究』(吉川弘文館、1980年) ▽所三男「木曽・飛騨の林業」(地方史研究協議会編『日本産業史大系5 中部地方篇』、東京大学出版会、1960年)
慶長7年、常陸国に50万石余りの所領を有していた佐竹義宣は、徳川家康から出羽国秋田・仙北地方(20万石)への転封を命じられました。転封直後の藩政を支えた人物の一人として有名なのが、家老を勤めた渋江政光です。渋江は、藩政執行の基礎となる検地政策に深く関わったことで知られており、慶長19年の大坂冬の陣で奮戦した末、鉄砲に撃たれて死去しました。この大坂冬の陣を前に、渋江は遺言として山林の大切さを説いたといわれています。江戸時代に入ってまだ間もない頃、渋江の眼には秋田の山々がどのように映っていたのでしょうか。 次に引用するのは、その遺言の一部分です。
| ○ | 御国は山川万ッ共に田畑の倍々の出物也。後々に至ては尽べく、今の三ヶ一にも成べし。左あれば、能き時と中の時と下の時と合せて備へを変じ、山林第一に備ふべし。往々草木には手支ふ事有るまじ。此儀巧者のものに能々心付べし。然れども、巧者のもの計りにて上にて知らざる時は用に立ず。今の如く郡役を立置き検地役を手に添せなば、山々尽る事あるまじ。此儀後々ともに申伝候儀肝要なり。(中略) |
| ○ | 国の宝は山也。然れども伐尽す時は用立ず、尽ざる儀、前に伝へたる如く郡役を立べし。必本を失はざる儀専一也。山々の吟味なき時は自尽る也、山の衰は即国の衰也、是を知る者希なり。(中略)何時も郡役に検地役を添しめて、田畠山川海野ともに諸色出物の事を肝要に取行はせなば、万代の御国と某考へたり。 |
| (「政光遺言 黒澤道家覚書」、『新秋田叢書』6所収) |
これによると、渋江は、「御国」(秋田藩)は田畑よりも山と川からの産物が豊富な土地柄であるが、今のように利用を続けていれば、資源は三分の一まで減少してしまうと述べています。そこで、特に山林については、時々の資源状況を勘案して郡役と検地役(「巧者」)に管理させ、第一に備蓄すべきであると主張したのです。その背景には、「国の宝」は山であり、山々が枯渇することは「国の衰」に繋がるのだという考えがありました。そして、後々まで郡役と検地役を配置して、山野や田畑・河海の産物を入念に管理させれば、「万代の御国」となるであろうと説いたのです。 渋江は、慶長8年に開始された久保田城の建設をはじめ、領内の土木工事などで森林資源が大量に消費されていく様子を目の当たりにし、山々が枯渇する将来を強く危惧したのだと思われます。検地政策に関与した渋江にとって、山々の枯渇は農政的見地からも大きな問題として認識されたことでしょう。山林は肥料となる草や若芽を供給するとともに、水源涵養機能を発揮して田の用水を確保するという重要な役割を担っていたからです。 江戸時代初頭にあって山々の大切さを明快に説き、その保護を強く訴えた渋江の先見性は、高く評価されるべきではないでしょうか。 〔太田尚宏〕 参考文献 ▽狩野亨二『江戸時代の林業思想研究』(日本林業調査会、1977年) ▽今村義孝監修『新秋田叢書』6(歴史図書社、1971年)
徳川家康の九男で尾張藩主となっていた徳川義直が、大御所の家康から信州木曽山を譲り渡されたのは、元和元年(1615)8月のことでした。 この木曽山加増をめぐっては、その年に義直の夫人として入輿した於春(浅野幸長の娘、のちの高原院)に対する「化粧料」であったという説が古くから口承されています。例えば、大正4年(1915)に刊行された『名古屋市史』政治篇第二でも、「又伝ふるところに拠れば、家康は此時義直の夫人浅野氏の化粧料として、信州木曽を義直に与えしかば…」(62頁)と記していて、この口承を紹介しています。 家康は同年4月4日、豊臣方と雌雄を決すべく駿府を出発、同月9日に尾張名古屋へと到着して、同11日に行われた義直と於春の婚礼を見届けた後、大坂へ向けて出陣していきます。そして「大坂夏の陣」で豊臣方を制圧し、凱旋の途次、再び名古屋へ立ち寄ることになります。 義直に木曽山が加増されたのは、この時の出来事でした。
| 一 | 御逗留之内、 御婚礼後日々御台所御費用之儀、 大御所様原田右衛門え御尋有之、一日黄金壱枚程之旨御答申上候処、駿府・羽州秋田・信州木曽之三ヶ所、運上一日黄金壱枚つゝ之由ニ而、木曽山被進之、且山村甚兵衛・同七郎右衛門・千村平右衛門、大御所様御前え被召出、木曽之地は宰相様え被進候間、左様可相心得旨、乍然材木之儀は、公義御用ニも可相立旨被 仰付之 |
| (敬公実録) |
上記の史料によると、名古屋に逗留中の家康が、原田右衛門へ「婚礼の後、御台所(於春)に対してかかる費用はどれぐらいか」と尋ねた際、原田が「1日あたり黄金1枚ほどです」と答えたところ、家康は、駿府と秋田それに木曽の3ヶ所は運上高が1日黄金1枚にあたるので、このうち木曽山を譲り与えると述べたとあり、さらに、木曽地方の支配を担当していた山村甚兵衛・山村七郎右衛門・千村平右衛門の3名を召し出して、①木曽の地を義直に与えるので、そのつもりでいること、②ただし材木については、公儀御用としても使うこと、の2点を申し渡したと述べています。 この「敬公実録」をはじめ、徳川林政史研究所に残る「事蹟録」「編年大略」「源敬様御代御記録」などの記録類を見ると、いずれも同様な記述が見られますが、これらはすべて後年の編纂史料であり、記述内容の信憑性については、一次史料の検討も含めた慎重な吟味が必要だといえるかもしれません。 この点に関して、『名古屋市史』政治篇の「第一」では、「家康亦八月十日、名古屋城に入るや、信濃木曽、及び美濃の地三万石を加封す、夫れ信濃、美濃交界の地、峻険にして要害を極む、尾張背面の保障として之を尾張藩に附せんこと、最も地の利を占むと云ふ可し、世に伝えて曰ふ、此時家康、義直夫人が一日に費す所黄金一枚なるを聞き、乃ち其代として木曽谷を加増すと、蓋し家康口を夫人の装筺料に藉りて其功に報いしならん」(99頁)と述べ、信濃・美濃の境界にある軍事的要衝を尾張藩に守衛させる目的で「美濃の地三万石」の加増が実施され、それを義直夫人の「装筺料」という口実で与えたのではないかという見解を示しています。この「美濃の地三万石」の加封が木曽山の譲与を示すものなのか等々については、なお検討が必要ですが、なかなか興味深い指摘といえましょう。 さて、せっかく木曽山を拝領しても、木曽山で伐採した材木を運ぶことができなければ、何の意味もありません。そこで次に、運材ルートの確保が問題となります。実は、尾張藩ではこの運材ルートの確保についても、面白い言い伝えが残されています。
| 尾張藩に口碑があった。口碑は家康が木曽を与えるとき、義直の家老成瀬隼人正に、「義直に木曽を与えるぞ」といったが、成瀬には聞こえないようすである。 家康はふたたび、「木曽を与えるぞ」と念を押すと、成瀬は初めて気がついたような顔をして、「ハッ、木曽の山・川とも御拝領、まことに有難く、おめでとう存じます」と義直に代わり、お礼を申し上げてしまった。 殿様に二言はない。家康が二度いったのは確かなので、成瀬の奇智で木曽と木曽川の二つを頂戴したというのである。 | |
| (徳川義親『最後の殿様』) |
もとより、こうした逸話が事実であるかどうかはわかりません。しかし、木曽山の森林資源を活用するには木曽川の流れが必須であったという認識が古くから存在したことを、このエピソードは示してくれていると思います。 山と川を一体のものとして保全し、これを上手に活用していくことが、江戸時代を通じた尾張藩の大きな役割の一つになっていったのです。 〔太田尚宏〕 参考文献 ▽『名古屋市史』政治篇第一・第二(名古屋市役所、1915年) ▽徳川義親『最後の殿様』(講談社、1973年) ▽所三男「化粧料『木曽山』考」(『徳川林政史研究所研究紀要』昭和54年度、1979年)
尾張徳川家には、山村甚兵衛と千村平右衛門という一風変わった立場の家臣がいました。ともに尾張家の大寄合という地位にありながら、同時に将軍家の表交代寄合並という格式をもち、いわば尾張家家臣にして旗本という両属の身分にあったのです。事実、山村・千村両家は江戸と名古屋に拝領屋敷があり、相続や隠居などの際には名古屋の殿様と江戸の将軍の両方に拝謁する必要がありました。 彼らがこうした立場におかれた理由としては、その成立事精が大きく関わっています。両家は、信濃国木曽谷の名家木曽氏の重臣でしたが、慶長元年(1596)に豊臣秀吉が木曽氏を改易したため没落し、他の木曽衆とともに関東各地を流浪していました。そうした中、慶長五年の関ヶ原合戦直前に転機が訪れます。会津上杉氏征討のため下野国小山にあった徳川家康は、石田三成挙兵の報に接して西国への進軍を決意します。このため、伊那路から木曽路を経て美濃路に至る東山道筋を確保する必要に迫られたのです。そこで家康は、山村甚兵衛と千村平右衛門の両人を小山に召し、木曽旧臣を糾合して同地を奪取するように命じました。両人は、さっそく東山道筋に進軍し、伊那路・木曽路・美濃路の城砦を次々と奪取、同地の平定に貢献します。 関ヶ原の戦い後、家康は両人の戦功に報いるため、山村・千村両人と配下の木曽衆に対して東美濃久々利付近に1万6000石余の領地を与えました。また、東山道制圧の実績を評価し、山村甚兵衛には木曽代官と木曽福島関所番を委ね、千村平右衛門を伊那谷の代官として榑木成村の支配を預けています。 ところが、山村・千村両家に再び転機が訪れます。元和元年(1615)、尾張国主となっていた初代義直に木曽谷と東美濃とが宛われたのです。あわせて、東美濃に所領をもつ山村・千村両家など木曽衆もまた、そのまま尾張家に「御附属」となる見込みとなりました。この際、山村家は、将軍から預かる木曽谷もまた尾張家領となるため、この「御附属」に直ぐさま従う決意をします。対して千村家は、将軍から預かる伊那谷が尾張家領となるわけではないことを理由に、このときの「御附属」に反対の意を表明しました。 この動きの最中、幕府は両家の由緒と実績を鑑みて、山村家へは木曽福島関所番の役目を、千村家へは榑木成村支配の役目を、これまでの通り委ねる決定を下します。この配慮により、千村家もまた尾張家御附属を受け入れる決心をすることになりました。こうして山村・千村両家は、所領という枠組みでは尾張家臣、役目の上では幕府直下の旗本となったのです。 尾張家と将軍家に両属する山村・千村両家のありさまは、江戸時代における主従関係が必ずしも明確ではなかった事実を教えてくれます。また、山村・千村両家といった存在を内包した尾張徳川家の多様性もまた同時に思い起こされて、非常に興味深いものがあります。 〔田原 昇〕 参考文献 ▽田原昇「近世伊那谷における榑木成村支配の様相」(『徳川林政史研究所研究紀要』第38号、2004年) ▽田原昇「山村甚兵衛家による木曽山林支配の様相」(『徳川林政史研究所研究紀要』第41号、2007年)
江戸幕府が山林保全の方針を明確に打ち出したとされる法令として、しばしばとりあげられるものに、寛文6年(1666)2月に発せられた「諸国山川掟」があります。 江戸前期の幕府法令その他を収載した「御当家令条」には、「山川掟」として、次のような史料を掲げています。
| 覚 山川掟 | |
| 一 | 近年は草木之根迄掘取候故、風雨之時分川筋え土砂流出、水行滞候之間、自今以後、草木之根掘取候儀、可為停止事 |
| 一 | 川上左右之山方木立無之所々ハ、当春より木苗を植付、土砂不流落様可仕事 |
| 一 | 従前々川筋河原等に、新規之田畑起之儀、或竹木葭萱を仕立、新規之築出いたし、迫川筋申間敷事 附、山中焼畑新規に仕間敷事 |
| 右条々堅可相守之、来年御検使被遣、掟之趣違背無之哉可為見分之旨、御代官中え可相触者也 | |
| 寛文六年也 午二月二日 | |
| 久 大和守 稲 美濃守 阿 豊後守 酒 雅楽頭 |
|
| (石井良助編『近世法制史料叢書』第二、161頁) | |
この「覚」の内容を要約すると、①近年では、草木の根まで掘り起こして取ってしまうため、風雨の際に川筋へ土砂が流れ込み、川の流れに支障をきたしているので、今後、草木の根を掘り取ることは禁止する(第一条)、②川上の左右の山で木立のないところには、今年の春より苗木を植えて、土砂の流出が起きないようにする(第二条)、③河原などへ新規の田畑を開く際、竹木や葭・萱などで築出し部分をつくって川筋を狭めてはならない(第三条)、④山中で新たに焼畑をつくってはならない(第三条付則)、⑤以上の項目を遵守すること、来年には検使を派遣して「掟」の内容に違反する者がないか見分をするので、その旨を代官たちへ触れるものである(あとがき)、といった感じになります。 差出人となっているのは、久世大和守広之・稲葉美濃守正則・阿部豊後守忠秋・酒井雅楽頭忠清の4名で、いずれも幕府の大老・老中たちです。 この「山川掟」をめぐっては、これを積極的に評価する立場と、限定的に評価すべきとする立場の意見があります。 積極的に評価する代表的な論者は大石慎三郎氏で、1977年に発表した著書『江戸時代』において、「山川掟」を「従来の“開発万能主義的農政”から本田畑を中心とする“園地的精農主義農政”に方向転換する」際の「接点」となったと指摘し(60頁)、17世紀前半までに進行した過剰開発によって頻発するようになった洪水などの自然災害に対する反省から、これ以上の開発を抑制し、「すでにできている古田畑をていねいに管理耕作することによって収穫を増やそうという本田畑中心主義政策」(63頁)への移行を促したと述べています。また同氏は、1995年の『貧農史観を見直す』においても、「幕府はこれ以上の開発を停止して、むしろ林野の保全のほうに力を移していく」(13頁)、と述べ、「山川掟」を「治山治水という国土保全の意図が反映された法令」(40頁)と位置づけています。 これに対して、「山川掟」の内容を限定的に理解すべきだとするのは、塚本学氏の研究成果です。塚本氏は1979年に「諸国山川掟について」という論文を発表し、その中で「山川掟」の性格について詳細に検討しました。 まず、第一条にある「草木之根迄掘取候」という行為について、大石氏が第三条と関わらせて、これを開発にともなう行為と理解したのに対して、塚本氏は、草や木の根を掘り取って商売にしていたという当時の実態を析出しています。
| 山々あらし候に付、縮被仰付御目付出候間、松長木ころ公儀刻印無之分は、売買に不仕様、百姓中並在々に有之頭ふり共に急度可被申渡候 | |
| 一 | 山によりかぶ木を伐、割木にいたす商売有之由に候、是又御停止に候間、可被申渡候 三月廿日 |
| 御算用場 | |
| 千秋彦兵衛殿 | |
| (改作所旧記) | |
上の史料は、『加賀藩史料』第参編に収められている寛文2年(1662)の達書です。この史料では、まず前段で、「山々あらし候」という理由により、加賀藩の刻印のない材木を売買してはならない旨を通達、さらに「かぶ木」を伐り出して「割木」に仕立てる商売についても、同様に禁止すると伝えています。この記述から、この頃の加賀藩の領内では、伐採した木の根株を掘り出して、薪などに用いると思われる「割木」をつくっていた者がいたことがわかります。
| 近年トモシ松高値ニテ、末々迷惑ニ付、半田山年々之御藪伐株根大分御座候、此分御野郡村々ヘ御掘ラセ被下候得ハ、大分トモシ松ノ御救ニ御座候、御掘ラセ被下候様ニト肝煎モ願申候、此前モ被達候事御座候由、堀出シ株根三分一ハ百姓掘手間ニ被遣候、三分二ハ入札ニテ代銀指上由ニ候、然共小松掘返シ御山ノ為ニ悪敷トノ儀ニテ其後止申由ニ御座候、然共此度被仰付候ハヽ随分大事ニ懸ケ、御山不荒様ニ肝煎共人足召連レ山入仕、掘セ申様ニ可仕候、其上小松少々掘返シ候ハヽ枯レ申候分幾度モ植直シ指上可申由申候事 | |
| (土壌山林竹木取締并訴訟抜書) | |
こちらは、『日本林制史資料・岡山藩』に収録された貞享元年(1684)の事例です。近年「トモシ松」(燃料用の松)の値段が上がっているので、半田山にある松の「株根」を掘り取って「トモシ松ノ御救」にしたいという願書の一部です。しかも岡山藩では、これ以前も松根の掘り返しが行われていましたが、「御山ノ為ニ悪敷」とのことで禁止されたとあります。このように、17世紀後半の各地では、木々の株根を掘り起こして薪などにする事例が多かったことが推測できます。 こうした実態を指摘して塚本氏は、「山川掟」第一条の「草木之根迄掘取候」という行為について、これを直接的に“開発行為”と結びつけることに対しては、懐疑的な姿勢を見せています。 また、「山川掟」が触れ出された範囲についても、塚本氏は諸本を検討した上、あとがき末尾部分の「御代官中え可相触者也」という文言が、「令条秘録」という史料では「御畿内並可被相守其趣者也」となっていることに注目して、「この禁令が代官宛のものと然らざるものとの二種があり、反面畿内を中心とした趣旨であったことを思わせる」(13頁)と述べ、さらに、これを補強するものとして万治3年(1660)に出された次の達書に着目しました。
| 山城・大和・伊賀三ヶ国の山々木の根掘候ニ付、洪水の節淀川・大和川へ砂押流埋候間、向後不掘木根様、其上以連々植苗木候様ニ急度可被相触之者也 万治三子三月十四日 美 濃 豊 後 伊 豆 水野岩見殿 五味備前殿 中坊美作殿 |
|
| (万大控抄) | |
これは、『日本林制史資料・津藩』に収められているもので、差出人はいずれも老中、宛所の水野は伏見奉行、五味は京都町奉行、中坊は奈良奉行です。塚本氏は、この達書が「山川掟」の第一条・第二条に連なっていくものであるとし、これが畿内周辺諸領に触れ出されていたことを明らかにしました。 言い換えれば、寛文6年(1666)の「山川掟」は、この万治3年令を強化したものと位置づけられ、その伝達範囲も淀川・大和川水系を中心とする地域であったと推定できるというわけです。「山川掟」公布の目的の第一は、淀川などの治水対策にあり、大石氏が主張するような全国的な“開発行為”を対象にした抑制策と理解するのは難しく、「諸国山川掟を以て全国の姿を類推するわけにはいかない」(22頁)と、塚本氏は述べています。 以上、大雑把ではありますが、「諸国山川掟」の評価をめぐる二つの学説を紹介してみました。環境保護の考え方が広く普及していく中、この「山川掟」を“江戸幕府による先駆的な環境保護政策”というように、非常に高く評価する考え方も時折見受けられますが、この法令の意義づけについては、より慎重な態度で臨むことが必要であるといえましょう。 〔田原 昇〕 参考文献 ▽石井良助編『近世法制史料叢書』第二(弘文堂書房、1939年) ▽大石慎三郎『江戸時代』(岩波書店、1977年) ▽塚本学「諸国山川掟について」(『人文科学論集』第13号、信州大学文学部、1979年) ▽佐藤常雄・大石慎三郎編『新書江戸時代3・貧農史観を見直す』(講談社、1995年)
無尽蔵ともいわれるまで豊富な樹木を擁していた森林地帯でも、秀吉・家康時代以来の相次ぐ用材伐り出しにより、17世紀後半には森林資源の枯渇が深刻化していました。 木曽山では、寛永期(1624~44)のはじめ頃には本谷筋で有用樹木が枯渇する「尽山」(つきやま)状況に陥ったとされ、それが次第に川筋をさかのぼっていき、寛永末年頃になると木曽川上流や支流の王滝川流域にまで波及したといわれています。尾張藩では、こうした状況に対処するため、同21年に本谷筋の一部の村々における榑木・土居・役木(年貢木)の伐り出しを禁止し、森林の温存を図りましたが、寛文5年(1665)には、より本格的な林政改革を実施して、木材利用と森林の保続の両立を目指しました。 このときの改革では、今まで木曽山での用材伐り出しを管轄していた山村家を材木支配から分離し、新たに上松材木役所を設置して伐木・運材に関わる事項を直轄化しました。また、寛永21年に伐採制限の対象となった村々(上松・須原・野尻・三留野など)や王滝村を中心として、有用樹種の繁茂する山々を「留山」(とめやま)に指定し、留山の範囲内でのすべての樹木の伐採を禁じました。この留山の設定範囲は、主として木曽川の本谷筋と王滝川の流域周辺であると推定され、同藩では慶長・元和期(1596~1624)に「尽山」化が進んだこれらの地域の森林の回復を意図して、留山政策を進めたものと思われます。なお、尾張藩ではこれとは別に、以前から鷹狩り用の幼鷹を採るための「巣山」(すやま)を各所に設けており、ここでも住民の立ち入りを禁止していましたので、巣山と留山はいずれも禁伐区として機能しました。 これらの巣山・留山は、貞享元年(1684)および享保年間(1716~36)に拡大され、留山が20か所、巣山が59か所となったものの、これらは木曽山全体の面積の5%前後に過ぎなかったといわれています。このほかの山は「明山」(あきやま)と呼ばれ、藩の御用材の生産や地域住民による自由な伐採と利用が許されていました。その意味では、この時期の禁伐区の設定は、木曽山全体から見れば必ずしも十分なものとはいえませんでしたが、初期の過剰な伐採への反省から森林の保護区域の設定へと一歩踏み出した点において、大きな意味があったと考えられます。 尾張藩の留山制度をはじめ、寛文期には土佐藩や津軽藩など有力な林業地域でも、直轄林の設定や山林管理の強化、樹木の伐採制限といった施策が次々と展開されました。これらはいずれも、戦国末から江戸初期にかけての乱伐による森林資源の枯渇に対応する政策でした。当初は誰もが「無尽蔵に存在する」と考えていた山々の樹木も、手当たり次第に伐り尽くしてしまうことによって、初めて「山の木々は管理しながら利用するもの」であったことに気づいたわけです。しかし、この時点ではまだ、諸藩による用材生産の機運は衰えを見せず、良材を求めて今まで未開発であった奥山へも進出して森林伐採を続けていくことになります。 〔太田尚宏〕 参考文献 ▽德川義親『木曽山』(私家版、1951年) ▽所三男『近世林業史の研究』(吉川弘文館、1980年)
江戸幕府が山林保全の方針を明確に打ち出したとされる法令として、しばしばとりあげられるものに、寛文6年(1666)2月に発せられた「諸国山川掟」があります。 江戸前期の幕府法令その他を収載した「御当家令条」には、「山川掟」として、次のような史料を掲げています。
| 凡そ山林は地の高陽に因りて草木の叢がる所、金鉄之生ずる所也。故に其の官を設けて、山林に入りて用木を取り、其の本木を材木とし其の末を薪とする事、各々土地に因りて其の制を定むる也。(中略)若し其の奉行を立つることなく、制法詳ならざるときは、民利をほしいままにして、其の杣取するに近く便りあるの処をのみ伐り取りて、山のあするに構はず、川のうまり水のあさくなるに構はず、唯だ一時の便用を利す。ここにおいて山林の材木年を追うて少なく、木を出す所遠くして其の要脚大につひえ、材木の買売尤も貴く、薪木次第に寡く、国用利せず。是れ山河に奉行なく、只だ民の利をほしいままにするゆゑん也。 (「山鹿語類」巻第十、『山鹿素行全集思想篇』第五巻所収、読み下し) |
| (「山鹿語類」巻第十、『山鹿素行全集思想篇』第五巻所収、読み下し) |
これによると、山鹿は山林を管理する役職を設け、その利用の仕方などについて、各々の土地に合った制度を定めるべきであると考えていました。もし、役職が設けられず、制度も充分に整えられていなければ、民衆は搬出に便利な近い山林ばかりを伐採し、森林資源が減少したり、土砂が流入して川が浅くなったりすることもいとわず、「一時」の利益を求めるものであるといいます。そして、こうした伐採が続けば次第に森林資源は減少し、伐採地も遠方になって運搬費がかさみ、結果的に「国」の利益とはならないのだと主張したのです。 山鹿の林政論で着目したいのは、地域性に即した林政を確立することで、民衆による森林資源の乱伐を抑止しようとした点です。つまり、森林資源は領主層の適切な管理によってのみ、保護・育成されると考えたのでした。具体的な政策としては、山林を計画的に伐採し、跡地には林を積極的に育成して、森林資源を枯渇させないようにすることを提言しています。 こうした山鹿の林政論は、多くの領主に影響を与えたといわれています。例えば、尾張藩木曽山における林政の基礎を確立した佐藤半太夫と、弘前藩の林政を確立した四代藩主津軽信政は山鹿の門人であり、桑名藩主松平定綱が藩政の方針を記した『牧民後判』のなかの「山林之制」も、山鹿の林政論をもとにしたとされています。 〔芳賀和樹〕 参考文献 ▽狩野亨二『江戸時代の林業思想』(狩野亨二、1963年) ▽所三男「林政史」(『社会経済史学』第10巻、第9・10号、1941年) ▽廣瀬豊編『山鹿素行全集思想篇』第5巻(岩波書店、1941年)
ここでは、山鹿素行の林政論に影響を受けた人物の一人として、弘前藩四代藩主津軽信政を挙げ、彼の林政思想を紹介したいと思います。 津軽信政は正保3年(1646)に三代藩主信義の三男として誕生し、明暦2年(1656)に家督を継ぎました。以後、宝永7年(1710)に死去するまでの55年にわたって津軽地方を統治してきました。 信政は、弘前藩歴代藩主のなかでも「中興の祖」と称されることがあります。その理由の一つとして、彼が在位していた時期に藩の機構や制度が多く整備されたことが挙げられるでしょう。例えば、寛文年間には津軽半島北部や岩木川下流域に広がる湿地帯の新田開発が大々的に行われたり、貞享4年(1687)には幕末まで藩の徴租の基準となる検地帳が作成されたりしました。 このように、藩の基礎を作り上げた信政は、山林に対しても独自の考えを述べています。彼の事蹟を記した史料によれば、ある時信政は、自分が大事に思うものが三つあり、その一つ目は家運、二つ目が嫡子、そして三つ目が山であると述べました。これらのうち、山と答えたのには理由があり、それを五行説を用いて説明しています。 信政によれば、人は五行(水・火・木・土・金)によって成り立っており、そのうち最も大事な要素が「火」であるとしています。しかし、「火」そのものには形がないため、形をなすには「木」によらなければならないとしています。さらに、「木」は人が身を置く「竃(かまど)の本」であり、そこを「万民性命を養う助となる」場所であると位置づけました。これらを述べたうえで、そうした「木」がある場所は「山」であるので、「山」を大切にしなければならないと結論づけています。 信政の林政思想の特徴は、五行説から「木」、さらには「山」の重要性を指摘した点にあります。五行説を用いてこれらのことを説明したのは、彼が山鹿素行の門人であることが強く影響しているでしょう。 それ以上に重要なのは、「木」が「万民性命を養う助となる竃の本」として位置づけられ、それ故に「山」を大切にしなければならないとしている点です。信政は「東奥の地は寒気猛烈なる故、山林に深く心を用いざれば成木難し。後世に至るまで上下よくよく山林に心を用ゆべし」と述べたとも言われています。これらのことを踏まえると、彼は薪炭や燃料の供給など、領民の日常生活を支えるものとして「木」や「山」を捉えていることがわかります。 信政は、領内の山林の乱伐を防止するため留山の制を定めたり、「仕立見継山(したてみつぎやま)」や「抱山(かかえやま)」などの山林を設定したりしています。弘前藩の山林行政の基礎は彼が在位している頃に概ね出来上がりました。 以上の点から、信政は津軽地方の気候・風土を把握したうえで、御用木の生産としての役割以上に、領民たちの生活に資するものとして山林を捉えていたと考えられます。そうした考えのもと、彼は長期にわたって山林を維持していけるような体制作りを目指そうとしていたのです。 〔萱場真仁〕 参考文献 ▽菊池元衛『信政公事蹟』(私家版、1898年) ▽狩野亨二『江戸時代の林業思想』(狩野亨二、1963年) ▽長谷川成一『弘前藩』(吉川弘文館、2004年) ▽長谷川成一『津軽信政 神に祀られた「中興の英主」』(弘前市立博物館、2015年)
森林の持つ最も重要な機能に水源涵養があります。これは、主に洪水や渇水を防ぐ働きを指します。 森林に雨が降ると、水は枝葉や幹を伝わってゆっくりと地表に到達し、堆積する落ち葉の層に吸収されて、やがて土壌に浸透します。土壌の浸透能力を超えた量の水は、地表を流れて河川へと注ぎます。優良な森林の土壌は、落ち葉などの有機物が微生物に分解されながら、土壌の粒子と混ざり合うことによってできる「団粒構造」が発達しています。 この団粒構造は、大小多数のすき間を持つ柔らかな構造で、水を良く浸透させて、地表を流れる水量を減少させます。地中に浸透した水は土壌中をゆっくりと移動し、徐々に河川に注ぐか地下水に加わることになります。したがって、良い森林を有する河川は、降雨直後にも急増水せず、晴天が続いても容易に渇水しないのです。日本は年間の降水量は多いものの、降水の大部分が梅雨期・台風期・降雪期に偏る上に、河川の勾配が急で水がすぐに海へと注いでしまいます。このため日本では、洪水・渇水を防止して、河川の水量を一定に保つ水源涵養の働きが極めて重要となります。 また、こうした水源涵養と密接な関係にある森林の機能が土壌保全です。団粒構造が発達した土壌は水がしみ込みやすく、地表を流れる水が減少するため、水が斜面の土砂を削り取り、河川へ流出させるのを防ぐことができます。さらに、地中に張りめぐらされた樹木の根が土壌や石を押さえているため、森林は土砂崩れの防止にも効果があります。 以上のように、河川の水量や土砂流出などが森林の状況と密接に関係していることは、古くから経験的に知られてきました。以下では、江戸時代における「治山治水」の取り組みについてみてみましょう。 江戸初期における城下町の成立・発展は、材木や燃料材としての薪炭の大量生産を伴い、鉱山の開発・発展にも、坑道を支える坑木や燃料材・還元剤である薪炭が大量に消費されました。森林の利用にあたっては、樹木を伐採するにとどまらず、薪などにするために根株まで掘り取る場合もありました。こうした材木・薪炭生産の一方で、大規模な新田開発は山野をも対象に展開しました。また、近世農業における肥料の主流は草肥であり、それを供給する草山を確保するために、伐採や火入れによって森林を草山にしたところもありました。そのため、17世紀後半になると、各地で森林の減少や荒廃が顕著となり、材木・薪炭に事欠くばかりか、水土保全機能の低下も問題となったのです。 こうした状況に対し、領主層は森林の保護・育成を図る政策を打ち出すようになります。幕府が山野の保護・育成を明示した法令としてしばしばとりあげられるのが、寛文6年(1666)2月に出された「諸国山川掟」です(「『諸国山川掟』の評価をめぐって」参照)。本法令の評価をめぐっては議論があるものの、幕府の治山治水への着目をうかがうことのできる内容だと思います。 このように、17世紀後半には治山治水の考え方が、支配階級のなかで影響力を持つようになってきました。当時における治山治水論の有力な論者に、熊沢蕃山がいます。熊沢は、「天下の山林十に八尽き」(『宇佐問答』)と森林の荒廃を危惧し、その問題点について、『集義外書』で次のように述べています。
| それ山林は国の本なり。春雨五月雨は天地気化の雨に候。六七月の間には気化の雨はまれにして、夕立を以て田畠を養へり。夕立は山川の神気のよく雲を出し、雨ををこすによれり。山は木ある時は、神気さかんなり。木なきときは、神気おとろへて、雲雨ををこすべきちからすくなし。しかのみならず、木草しげき山は、土砂を川中にをとさず。大雨ふれども木草に水をふくみて、十日も二十日も自然に川に出る故に、かたぐもつて洪水の憂なし。山に草木なければ、土砂川中に入て、川どこ高くなり候。大雨をたくはふべき草木なきゆへに、一度に河に落入、しかも川どこ高ければ、洪水の憂あり。 |
| (「集義外書」巻一、『増訂 蕃山全集』第2巻所収) |
これによると、熊沢は山林は国の根本であり、山に木があれば雨が降りやすいと考えていました。さらに、山に草木があれば、土砂の河川への流出が抑制され、水もゆっくりと川へ注ぐので、洪水の心配がいらないと主張しました。逆に、山に草木がなければ土砂が流出して川床が高くなり、水も一気に川へ流れ込むため、洪水が起こりやすいと指摘したのです。このように、熊沢は森林の持つ水土保全機能を重視し、その低下を危惧していました。荒廃した山林を回復する方法として、熊沢は伐木の停止と造林、計画的な伐採を主張しました。 この熊沢の治山治水論は、支配階級に大きな影響を与えました。例えば、太宰春台の『経済録』は蕃山の論を踏襲したものといわれます。また、田中丘隅の『民間省要』や蓑笠之助の『農家貫行』でも蕃山の論がとりあげられました。 〔芳賀和樹〕 参考文献 ▽只木良也『新版 森と人間の文化史』(日本放送出版協会、2010年) ▽狩野亨二『江戸時代の林業思想』(狩野亨二、1963年) ▽所三男「林政史」(『社会経済史学』第10巻、第9・10号、1941年) ▽正宗敦夫編『増訂 蕃山全集』第2巻(名著出版、1978年)
熊沢や山鹿の林政論は、治山治水や藩財政への寄与という見地から、造林や計画的な伐採を主張しましたが、その技術については深く言及していません。これらの技術が具体的に論述されたものが「山林書」です。 元禄期(1688~1704)以降、小農経営をより充実させるために、主穀生産を基調にしつつも多くの作目の栽培技術を示し、その一環として植林技術を記した農書が数多く登場しました。宮崎安貞の『農業全書』はこの代表です。その後、林業技術を単独で取り上げた山林書が、極めて少数ですが登場します。農書の書き手に農民出身者が多数存在したのに対し、林業を単独で扱った山林書の書き手は支配階級ばかりでした。支配階級がそれぞれの地域の自然・市場・社会などの条件に合わせて、造林や計画的な伐採に関する技術についての大系を考案し、これを記録して残したものが、林業を単独で取り上げた山林書です。 このうち、以下では、領主の林政論を具体化し、領主林の合理的な経営方法を示したものとして、萩藩の『弐拾番山御書付』と琉球王国の『林政八書』の内容を紹介します。また、林政論の影響を受けつつ、国産奨励策の見地から造林技術をまとめたものとして、盛岡藩の『山林雑記』と黒羽藩の『太山の左知』をとりあげましょう。
| ○萩藩『弐拾番山御書付』 萩藩では、17世紀末から財政難が表面化し、御立山と称される領主林から盛んに立木が伐採・販売されました。そのため、享保4年(1719)には森林資源の減少が顕著となり、輪伐による御立山の持続的利用が図られるようになりました。輪伐とは、森林資源の持続的利用を図る森林経営の方法です。しかし、それは充分に機能しませんでした。 そこで、寛保3年(1743)、当職という重職にあって財政再建に取り組んだ山内広通は、御立山における輪伐の計画をより有効なものに立て直しました。この輪伐の内容をまとめ、今後の御立山経営の指針とすべく作成されたものが『弐拾番山御書付』であったのです。本書は、近世における輪伐の具体的内容を詳細に示した極めて貴重な文献です。 |
| ○琉球王国『林政八書』 明治18年(1885)、沖縄県が林政の規範として旧王国時代の林業技術書・森林法令のうち重要な8点を選んで編纂したものが『林政八書』です。そのうち基本となる7点の山林書は1737~51年に成立しており、首里王府の最中枢の役職・三司官にあった蔡温の指導下で作成されました。蔡温は農業振興の前提条件となる治山治水と、建築材・造船材などの林産物自給を目指して杣山の充実を図った人物です。杣山とは、近世日本の領主林と類似のものでした。 『林政八書』のうち、基本となる7点の山林書では、風水を取り入れた造林地の選定やさまざまな造林法が説かれています。例えば、造林地を囲む尾根を「抱護」と呼び、その内部には森羅万象の根源である「気」が充満して諸木の成長が旺盛になると考えられていました。また、天然更新の具体的方法として説かれた「山工之正法」は、多様な樹種が混交する亜熱帯林に適したものでした。 |
| ○盛岡藩『山林雑記』 『山林雑記』(上・下)は、盛岡藩で山林奉行や諸木植立吟味役などを勤めた栗谷川仁右衛門が書き残した複数の造林書と、藩林政の事例集からなっています。上巻に含まれている造林書は、天保13年(1842)から安政5年(1858)までの間に成立したもので、造林奨励のために記されたものです。 栗谷川は、有用樹種であるスギの植林に注目し、寒冷地である盛岡藩に適した方法を追究して、植栽地の地形と土壌の選定について重点的に論じました。また、農民経営を補完するため、工芸作物である四木や果木などの植栽方法も具体的に示しており、国産奨励の意図が窺えます。 |
| ○黒羽藩『太山の左知』 黒羽藩では享保期(1716~36)以降農村の荒廃が進み、その復興策として農業以外の特産物生産と江戸への販売が奨励されるようになりました。材木生産もその一つで、寛政期(1789~1801)からは部分林による造林が奨励されました。このとき重要な役割を果たしたのが重臣の興野隆中です。彼は造林法を研究してスギの造林を進め、その養子である隆雄も造林の研究・実践に励みました。この父子二代にわたる研究の真髄を、嘉永2年(1849)にまとめたものが『太山の左知』です。 興野父子が確立した造林法で、最も画期的な技術が実生苗の育成です。従来黒羽地方の造林は、自生したスギ苗を抜いてきてそれを育苗する山引苗に依存していましたが、造林の奨励などで大量の苗木が必要となり、種子から育苗する実生苗の技術が不可欠となりました。 また、植林法については、藪の中や樹下への植栽と、広い植え間が特徴的です。この植林法のうち、前者は那須地方の乾燥や寒風害から苗木を守るために合理的でした。後者は、黒羽藩が大市場の江戸から遠く、板材を生産できる大径木のみに商品価値があったため、早く大径木を得られる広い植え間が選ばれたと考えられます。 また、『太山の左知』には先進的な大和国吉野林業に関する記述も散見されます。しかし、隆雄は吉野と黒羽藩の自然や市場の条件差を比較分析し、安易に吉野を模倣せず、黒羽藩に適合した技術の確立を目指したのでした。 |
〔芳賀和樹〕 参考文献 ▽加藤衛拡「共生時代の山利用と山づくり―近世山林書の林業技術―」(山田勇編『 森と人のアジア―伝統と開発のはざまに生きる―』昭和堂、1999年) ▽佐藤常雄ほか編『日本農書全集』56、林業1(農山漁村文化協会、1995年) ▽佐藤常雄ほか編『日本農書全集』57、林業2(農山漁村文化協会、1997年)
高山藩時代の飛騨国は、「山内残らず地頭山」という建前となっていて、若干の百姓稼山を除いて、ほとんどの山林は領主の掌中にあり、藩直営の「出雲守御台所木」生産や「商人請負木」と呼ばれる請負生産によって木材の伐り出しが行われていました。

飛騨国は、大野郡・吉城郡・益田郡の3郡で構成されています。飛騨国を流れる河川は、中央部にある分水嶺を境に、庄川・宮川・高原川など日本海側へ流れるものと、飛騨川・馬瀬川など木曽川を経て太平洋側に至るものとに分けられます。伐り出した木材を川に下ろして運搬する必要から、こうした地理的条件にしたがって生産地帯が区分けされ、北流して日本海側へ運材する地域を「北方」、南流して太平洋側へ運材する地域を「南方」と呼びました。そして、北方の林業地域は、西部の白川山を中心とする庄川流域と、東部の高原山を中心とする高原川流域とに二分されていました。 江戸幕府は、元禄5年(1692)に飛騨国を幕領に編入した後、基本的には高山藩時代の林野政策を受け継いで、地頭山を御林に組み込み、御用材の確保を目指しました。元禄15年(1702)に行われた御林改めでは、499か所の御林を設定し、このうち155か所を御留山、40か所を伐跡留山に指定しています。 幕領編入後の幕府による御用材の伐り出しは、「出雲守御台所木」を引き継いだ地元山方による生産と、「商人請負木」を継承した請負生産の双方を並行して行わせる方式をとりました。 高山藩の「出雲守御台所木」生産は、山方や高山の杣頭を通じて杣稼農民に金銀・米・味噌・塩を前貸しして諸材木を伐り出させ、金森氏がこれを定値段で買い取って差引勘定をするというものでした。一方の「商人請負木」は、あらかじめ定められた木品の値段と請負量に基づいて商人が前掛金を上納し、伐採事業の完了後、実際の数量・寸法を改めたうえ、請負人から代銭をとって清算するのと引き替えに材木を渡すというものでした。高山藩時代の商人請負は、隣国である加賀・越中の商人による北方山内(白川山・高原山)での伐採、高山商人による南方山内(阿多野・小坂・久々野など)の請負が主流でしたが、幕領編入後は、地元や隣国の商人の名前が姿を消し、江戸商人による請負が圧倒的多数を占めるようになり、収公直後の元禄6~7年(1693~94)には、南方山で白子屋・奈良屋が、北方の高原山で大岡屋・岡村屋・大文字屋などが請負生産を開始しています。 江戸商人の請負による木材の伐り出しは、他国の杣を大量に引き連れ、幕府から請け負った御用木のみならず、幕府の権威を背景にして自己売買用の売木をも強引に伐り出すという略奪的伐採であったため、請負山の山林資源の枯渇は著しいものとなりました。また、請負事業により多数の人口が国内に流入したため、米が払底して米価の高騰が著しく、飛騨国内の人々の生活を圧迫する結果をもたらしました。 一方、幕府は当初、地元山方による木材の伐採も許可し、元禄10年(1697)・同11年には、榑木70万挺・同60万挺の伐り出しを許しましたが、元禄14年になると「当分山稼差留置」として地元山方の伐木を停止する旨を通告したため、国内の人々の窮迫はいっそう顕著なものとなりました。そこで山方の農民は、宝永2年(1705)に代表を江戸へ送って商人請負の中止を嘆願した結果、請負中止は認められませんでしたが、年間60万挺の榑木生産の再開が許可されることになりました。さらに、商人請負の年季明けを迎えた正徳3年(1713)には、再契約の阻止運動を展開し、老中秋元但馬守喬知への駕籠訴を行うなどの抵抗を続け、この年には南方山における商人請負の継続が認められないこととなり、幕府直営による元伐の制度が整えられました。商人請負は、その後も北方の山々で継続されていましたが、享保12年(1727)に代官長谷川忠国により白川山での商人生産が中止されて請負による伐採が廃止され、一方で地元山方による伐り出しを南方山に限定し、年間伐採金高を7500両とする定式元伐の方式が整備されました。 〔高橋伸拓〕 参考文献 ▽『岐阜県史 通史編近世 下巻』(岐阜県、1972年) ▽所三男『近世林業史の研究』(吉川弘文館、1980年) ▽田上一生『岐阜県林業史 上巻(飛騨国編)』(岐阜県山林協会、1984年) ▽太田尚宏「飛騨国山林地域における元伐生産と御榑木方地役人―宝暦期を中心に―」(『徳川林政史研究所研究紀要』第37号、2003年)
飛騨国は、高山藩時代に木が乱伐され、また、江戸幕府の直轄地となった後も御用木が大量に生産されたため、木材資源が次第に枯渇していきました。このような状況のなかで、飛騨代官亀田三郎兵衛は享保6年(1721)に、同じく幸田善太夫は延享3年(1746)に、植林政策を発令しました。これは、飛騨国で初めて実施された植林政策で、他の幕領と比べても早い時期に行われたものでした。以下では、それぞれの政策の内容についてみていきたいと思います。 まず、亀田三郎兵衛の政策を次の史料からみてみましょう。
| 差上ヶ申証文之事 | |
| 一 | 飛州村々橋并井堰入用之木前々より取尽申ニ付村々木苗立置、後々右入用ニかきらす御用ニ立申様ニ可仕旨此度別而被仰付奉畏候、則 村々ニ而植申候員数重而御改を請可申候、麁末ニ致置他村之木を願出候ハヽ御吟味之上急度可被仰付候由奉畏候、為後日証文仍如件 享保六丑年 |
| (享保6・7年「村々木苗植候証文」 岐阜県歴史資料館所蔵) | |
この史料によると、飛騨国内で必要な橋や井堰の普請用材が不足しているため、村々へ苗木の植え付けを指示している様子がうかがえます。飛騨国では大量の木が伐り出されたことによって、このような問題が生じたのです。これは飛騨3郡の各村に割り当てられ、益田郡は100か村、大野郡は53か村、吉城郡は8か村が課されました。苗木の樹種は、檜・椹・杉・黒部・ひば(檜葉)でした。亀田の植林政策は、飛騨における植林政策の端緒となるもので、初めて育林が志向された重要な施策といえます。 次に、幸田善太夫の植林政策をみてみます。幸田善太夫の植林仕法は、①村役、②高懸、③人別割という方法がとられました。①村役では、対象は飛騨3郡397か村で、1村につき35本を割り当て、計1万3960本となります。②高懸では、組高100石につき24本を割り当て、計8187本となります。ただし、材木・榑木稼を行っている114か村は、高懸は除いて人別で割り当てました。③人別割では、榑木稼114か村・1万8500人余を対象に、100人につき65本を割り当て、計1万2185本となります。以上のような方法を用いて、高山役所は、飛騨3郡397か村に3万4006本を割り当てました。 それでは、幸田はどのような理念のもとに、この政策を実施したのでしょうか。延享3年「飛州三郡村々植苗木留」(岐阜県歴史資料館所蔵)によると、幸田の政策は、植林による山稼ぎの相続、国内での普請材木・家作木の確保、苗木の生成による御用木や村々の利益の確保という理念のもとに発令されたことがわかります。 さて、亀田・幸田の植林政策は、発令後どうなったのでしょうか。亀田・幸田の政策の経過をまとめた、寛政元年「亀田様・幸田様御支配之節村々植木帳」(徳川林政史研究所所蔵)からは、以下のようなことがわかります。 亀田の政策は、1年のみ行われました。3郡全体で9159本を植え付けて、樹種は、檜・椹・杉・松・黒部・ねず・栗・ひば・樅・樫がみられます。一方、幸田の政策は、延享3年から寛延2年(1749)までの4年間にわたって行われました。3郡全体で1万6312本を植え付けています。樹種は、檜・椹・杉・松・黒部・ひば・姫子・栗・槇・樅・栂がみられます。このように、さまざまな樹種の木材資源の補充が行われた点に政策実施の意義があったといえます。ただし、この段階での植林は、育成的林業の転換点ではありましたが、計画的といえるほどまでの状況は確認できず、育林の模索段階であったものと捉えられます。 こうして、飛騨国では育林が志向されるようになりましたが、木が成木になるまでには長い年月が必要で、その生成が図られる間にも御用木の生産は行われました。これによって、飛騨では木材資源の枯渇が一層進み、御用木の生産を中止にする休山策の発令に踏み切られることとなるのでした。 〔高橋伸拓〕 参考文献 ▽『岐阜県史 通史編近世 下巻』(岐阜県、1972年) ▽所三男『近世林業史の研究』(吉川弘文館、1980年) ▽田上一生『岐阜県林業史 上巻(飛騨国編)』(岐阜県山林協会、1984年) ▽高橋伸拓「飛騨幕領における木材資源の枯渇と植林政策―享保~延享期を中心に―」(『徳川林政史研究所研究紀要』第43号、2009年)
天保12年(1841)7月、勘定奉行梶野良材は御林改め令を発令しました。このとき発令された御林改め令は、寛政4年(1792)の御林改め令とそれに新たな条項を付け足したものとなっています。この法令では、①御林帳の改め、②風損・立ち枯木などの取り計らいの伺い、③苗木の植え付け(木1本伐り採りにつき、3本植える)を指示しています。②・③がこの時に追加された内容となります。本法令は、天保改革の一環として行われたものでした。 飛騨郡代豊田友直は、勘定奉行梶野良材の天保御林山改め令を受けて、同年8月、材木伐出しの見分をし、次のようなことを自身の「日記」に記しています。
| ○ | 当時御材木伐出し候山々之内、此小坂を第一とす、中山亞ク之小坂は御嶽続キ之深山ニ而、人家を離レ信州境迄七里余あり、近来山中追々伐リ荒シ良材立といへとも此山中ニある檜材猶百万本は不減といへり、飛国は毎々日記えもしるす如く、険山陸続屏立して平美之地稀ニ而也、故ニ此国ニ生する所之五穀、此国之民を育するニ足らず、尤下国と云べし、されとも良材を出スこと我国ニ冠たるは皆人々所知、宜しく苗木培養して非常に備候義、御政治中要務之一端と云べし |
| (「豊田友直日記」 東京大学法学部法制史資料室所蔵) |
上記の史料によると、豊田は植林をして非常に備えることが、重要な任務の一つと考えました。そして、後のことを考えていないこれまでの仕法に問題を感じて、同9月17日、豊田は自身で植林の仕法を定めて、これを益田郡山方の47か村へ通達したのでした。 豊田の政策の特徴については、これが天保改革期に行われた点をふまえる必要があります。勘定奉行梶野の苗木植付事業は、信州伊那山でみられるように、幕府からの資金提供によって行われたものでした。しかし、豊田は資金提供を受けず、村側の負担により、植林を実施したのです。これは、豊田独自の政策として位置付けられ、豊田が天保改革に批判的立場をとっていたことと関係するものと思われます。 豊田の植林仕法を受けて、益田郡山方の中山筋22か村と山方25か村は、天保12年から仕法の内容を具体化していき、同13年から実際に植林を実施しました(~嘉永7年)。役所側が「山方相続」、つまり山方百姓の生業維持のために植林を実施するという意向を示し、村側は積極的に動き、苗木の割当方法は村側の主張によって軒別割(1軒につき50本)が採用されました。村側が豊田の仕法を発展させて行ったのでした。村々の植林の実態をみると、苗木の植え付け状況から2つの時期に分けることができ、政策も一定したものではなく、変化していました。 第2期になると、村の対応はそれぞれであり、組ごとで対応に違いがみられるようになります。また、この時期は植え付ける苗木の数を減らし、それまで植えた苗木の手入れを行う養育期へ移行したものと捉えることができます。 以上から、勘定奉行の政策路線にのらない豊田独自の政策実施と、生業維持のために仕法を発展させるなどの村側の積極的な動きにより、植林は継続して行われ、豊田の植林政策によって成功といえるほどの大量の苗木を植え付けることができたのでした。この後、豊田の政策は、飛騨郡代福王三郎兵衛が山見重役制を導入し、彼らの献策によって実施された植林仕法によって中止となりましたが、福王の次の郡代増田作右衛門が豊田の仕法に戻して、植林を継続しました。こうして、豊田の政策を基本として、植林は実施されていき、幕末期の飛騨「御林山」の林相の回復へとつながったのでした。 〔高橋伸拓〕 参考文献 ▽『岐阜県史 通史編近世 下巻』(岐阜県、1972年) ▽所三男『近世林業史の研究』(吉川弘文館、1980年) ▽田上一生『岐阜県林業史 上巻(飛騨国編)』(岐阜県山林協会、1984年) ▽高橋伸拓「飛騨幕領における植林政策の展開―天保~嘉永期を中心に―」(『徳川林政史研究所研究紀要』第42号、2008年)
江戸城は後北条氏の支城の一つでしたが、天正18年(1590)、豊臣秀吉の関東進攻により後北条氏が滅亡すると、その旧領は徳川家康に与えられ、家康は江戸城を居城に定めました。 江戸城が将軍の居城となると、工事には全国の諸大名に助役を賦課する御手伝普請の形式がとられました。まず慶長8年(1603)には70余家の大名が動員されて江戸市街の大拡張工事が行われ、つづいて同11年には西国諸大名に城郭の大拡張工事が命じられ、本丸御殿、二丸・三丸・石垣などが築造されました。さらに翌12年には、関東・甲信越・奥州の諸大名が工事を続行するとともに、五層の天守閣が建設されました。これらの工事によって江戸城は大城郭としての形をととのえたものの、なお工事は継続され、元和8年(1622)の本丸御殿改築、寛永元年(1624)の西丸御殿造営、同12年の二丸の拡張と三丸の縮小を経て、同13年の大規模な外郭修築工事によって江戸城の総構が完成しました。 江戸城の総構は、武家地・町地・寺社地が配された外郭と、狭義の城内である内郭とに大別されます。内郭は本丸・二丸・三丸からなる本城と、西丸・紅葉山・山里からなる西城、および吹上御庭などにより構成され、内濠によって囲まれていました。 このうち、本丸には本丸御殿と天守閣がありました。本丸御殿はいうまでもなく、将軍の住居と幕府の政庁を兼ね、天守閣は外観五層、内部は地階(穴蔵)をふくめると六階でしたが、明暦3年(1657)の大火で焼失したのちは再建されず、天守台のみがのこりました。本丸御殿は明暦の大火後、万治2年(1659)に再建され、その後、天保15年(弘化元年・1844)・安政6年(1859)・文久3年(1863)の三度焼失し、2回造営(弘化2年・万延元年)されましたが、最後の文久3年の罹災後は再建されませんでした。 西丸には大御所もしくは将軍の世子が住む西丸御殿があり、同御殿は文禄3年(1594)の創建以来5回焼失し、造営・修築は7回におよんでいます。とくに、幕末の元治元年(1864)に再建された建物は仮御殿でしたが、既述したように、文久3年に本丸御殿が焼失したあと再建されなかったため、以後この仮御殿が将軍の住居兼幕府の政庁として使用されました。 以上のように、本丸御殿と西丸御殿は何回か火災で焼失し、そのつど再建されました。ここでは、天保9年(1838)3月10日に焼失した西丸御殿の再建と、用材の調達についてみてみましょう。炎上当時の西丸御殿は、その前年の4月、将軍職を次男の家慶に譲って隠居した家斉の居館でした。しかし、大御所家斉は、依然幕政の実権を握っており、西丸御殿は、事実上の幕府政庁でもありました。したがって幕府は、時を移さず再建に着手しました。火災の3日後の3月13日には、首席老中水野越前守(忠邦)を西丸御普請惣奉行に、若年寄の林肥後守(忠英)をその副奉行に据え、同じ日に作事奉行・小普請奉行・勘定奉行などをその下の普請奉行に任命、属僚には勘定組頭・大工頭・作事下奉行などが命じられました。 さらに4月10日、勘定吟味役川路三左衛門(聖謨)が「御普請御用」を仰せ付かり、みずから裏木曽(川上・付知・加子母の三か村)に出向いてヒノキの良材を調達することになりました。彼は4月22日に江戸を出発し、熱田白鳥での撰木を済ませてから、5月6日裏木曽の「出之小路」に入山、ここの山小屋に滞在して伐木作業を督励したのち木曽諸山を見分、6月14日ふたたび「出之小路」へ戻って伐木・運材作業の促進を図り、7月12日江戸へ帰参しています。 「出之小路」山は、比類のない大ヒノキの群生地として尾張藩に手厚く保護された「不入山(囲い山)」でした。実際に同所で伐り出された用材の数量とその規格は、「近来世珍録」に次のように記されています。
| 一 | 今度伐り出したる桧材の内、長さ九尺先にて指し渡し三尺の材、小口にて木目かぞえ見れば、千年の余に見ゆる由。 |
| 一 | 今般御伐り出しに成りたる材木、大旨左の通り |
| 一 | 桧大材の分三百本〔長さ三間より九間迄の材〕、元口〔二尺三寸より五尺六寸迄〕、末口〔一尺八寸より三尺六寸迄〕、此の内長さ九間二本。長さ八間の材壱本。此の内にも殊に大木延べのよき第一番の木カナテコと呼びたるは、長さ十三間余、元口にて五尺六寸、廻り壱丈七八尺有り。此の山内に此の上の大木なし、木目をかぞえ見れば千年の余に見えたり。かほどの大材は伐残の内になし。寔におしき事也。 |
| (「近来世珍録」、『東京市史稿』第3巻所収、読み下し、〔 〕内は割註箇所) |
主にヒノキの大材300本が採出されていますが、この中には樹齢1000年を超える大物もありました。しかし、この大材が江戸へ到着したときには、西丸御普請は大方竣工していました。 〔深井雅海〕 参考文献 ▽所三男「江戸城西丸の再建と用材」(『徳川林政史研究所研究紀要』昭和48年度、1974年) ▽深井雅海『図解 江戸城をよむ』(原書房、1997年) ▽『わかりやすい岐阜県史』(岐阜県編纂・発行、2001年)
森林の減少が問題視されるようになった17世紀後半には、各地で輪伐法(りんばつほう)と呼ばれる方法が立案されるようになりました。輪伐法とは、長期的な伐採計画のことで、たとえば森林が回復するまでの年数を30年と見積もった場合、その山林を30か所に分けて毎年均等に利用していけば、30年後には最初に伐採した場所で山林が回復し、再び利用できるようになります。これを繰り返して、山林の利用と回復のバランスを保とうとしたのが、江戸時代の輪伐法です。 この輪伐法は各藩によって名称がさまざまで、弘前藩では「廻り伐」「順伐」、秋田藩では「番山繰」、仙台藩では「廻り伐」「順繰伐替」、米沢藩では「順ぐり」、水戸藩では「順伐」、土佐藩では「順番」、萩藩では「番組」「車採用」、対馬藩では「廻り伐」「順伐」などと呼ばれていました。 このように江戸時代には各地で輪伐法が考案・実施され、森林の持続的利用が模索されましたが、その具体的な内容を知らせる史料はほとんど残っていません。ここでは、その貴重な事例として、萩藩の御立山と、秋田藩の銅山掛山で実施された輪伐法を紹介しましょう。 まず萩藩の輪伐法です。同藩では、17世紀末期に財政の窮乏が表面化し、これを補うために御立山(藩の直轄林)から樹木が盛んに伐採されました。その一方で、森林の減少を防ぐ施策はとられなかったため、御立山の森林は次第に枯渇していきました。 そこで藩は、享保4年(1719)になると御立山を20に区分し、その樹木を毎年順番に村人や商人らに入札販売する「二十割之仕法」を立案しました。さらに寛保3年(1743)には、「当職」という重職にあって藩財政の再建に取り組んでいた萩藩士の山内広通が、「番組山之仕法」と呼ばれる新しい輪伐計画を立て直しました。この「番組山之仕法」では、充分に生育していない若木などを除き、藩内の御立山の約4割が輪伐計画に組み込まれ、伐採跡地における森林の保護・育成も重視されました。ところが、実際には財政補填のために伐採量が計画量を上回るようになり、この「番組山之仕法」は思うように進みませんでした。 しかし、藩はこれで森林の持続的な利用を諦めたわけではありません。その後も延享4年(1747)、宝暦10年(1760)、安永4年(1775)と輪伐計画を繰り返し立て直しては、森林の持続的利用に努めました。萩藩の輪伐法は、森林を枯渇させない範囲内で、いかに森林を財政再建に役立てるかを考えた役人たちの苦労の結晶といえそうです。 次に秋田藩の輪伐法をみてみましょう。同藩には、江戸時代最大級の銅山である阿仁(あに)銅山がありました。江戸時代の銅山では、掘った坑道を支えるための材木に加え、銅鉱石から純度の高い銅を取り出すために大量の薪炭が消費されました。このため、寛文10年(1670)に阿仁銅山の開発がはじまると、周辺の森林はみるみるうちに減少してしまいました。そこで元文5年(1740)、藩は阿仁銅山の周辺に「銅山掛山」という専用の森林を設定してその保護を命じ、さらに宝暦12年(1762)には「番山繰」と呼ばれる輪伐法を立案しました。 こうした銅山掛山における番山繰の立案は、阿仁銅山へ材木・薪炭を安定供給するための画期的な施策であり、その後も森林の状況や銅の生産量の推移に応じて、臨機応変に計画が修正されました。特に天保期(1830~44)に修正された炭用の番山繰は、なんらかの理由で計画通りの製炭ができない場合を考慮し、予備の森林を用意しておく実践的なものでした。さらにこの番山繰は、製炭に不向きな針葉樹を伐採するなど、炭焼きに適した山林の育成とあわせて実施されました。こうした施策が奏功して、銅山掛山の森林は幕末まで枯渇することなく、阿仁銅山は長期にわたる産銅を継続できました。 このように江戸時代には、植林だけでなく、限りある森林を持続的に使うための工夫として輪伐法が考案されたのです。 〔芳賀和樹〕 参考文献 ▽徳川宗敬『江戸時代に於ける造林技術の史的研究』(地球出版、1941年) ▽脇野博『日本林業技術史の研究』(清文堂出版、2006年) ▽芳賀和樹「近世阿仁銅山炭木山の森林経営計画―天保14年炭番山繰を中心に―」(『林業経済』756、2011年)
ここでは、代表的な領主的林業地帯の一つである秋田藩をとりあげて、領主による材木生産の展開についてみていきたいと思います。 秋田藩では、江戸初期から城下町の建設や鉱山開発、幕府から賦課された板材の上納などのために大量の材木が伐採されました。また、材木の領外への売却も進められました。同藩のなかでも特に優良なスギを豊富に擁し、材木生産が盛んであったのが領内北部の米代川中・上流域です。元和~寛永期(1615~44)に、この地域で生産された材木の売却代は、1か年銀200~300貫目におよびました。こうした材木生産の展開によって森林資源が減少すると、藩は御留山制度を設けるなど、資源の保護に力を入れるようになりました。 延宝5年(1677)になると、盛岡藩と境界を争っていた米代川上流の長木沢が秋田藩領として確定しました。長木沢は特にスギが豊富に成育していた地域であり、のちに領内第一の山林と位置づけられました。以後、宝永期(1704~11)頃までは、長木沢から極めて大量な材木が生産されました。この時期は、米代川中・上流域で生産された材木の売却代は1か年銀約1000貫目におよび、材木生産の最盛期となります。しかし、同時に森林資源の減少も進行したため、宝永期には植林政策が開始されました。 その後、正徳~享保期(1711~36)頃を境にして、米代川中・上流域の材木生産量は次第に減少するようになりました。ただし、寛保期(1741~44)からは男鹿山の伐採が新たに開始されたこともあってか、明和期(1764~72)までの生産量は比較的豊富でした。米代川中・上流域と男鹿山から生産された材木の材種は多様でしたが、領外への売却において特に重要であったのが、大材から生産される保太木(丸太を割った材木)です。しかし、森林資源が減少して大材が欠乏したため、明和期を最後に保太木は生産されなくなりました。 江戸初期における米代川中・上流域の材木生産は、米代川流域の御材木郷と称された村々に対して、藩が材木の納入を強制する形で実施されました。御材木郷に対する材木生産の賦課という形はしばらく変化しませんでしたが、のちに伐採した樹種と量に応じて、村に米(木本米)を支給するようになりました。しかし、伐採地が次第に奥山となったため、伐採経費が増大して、規定の木本米だけでは村の負担が大きくなりました。そこで、御材木郷は正徳2年(1712)から数度にわたって木本米の増量を藩に訴え、寛延2年(1749)には材木生産賦課の廃止を願い出ました。この結果、翌3年には材木生産の賦課は廃止され、入札による請負制へと転換しました。 江戸後期における材木の入札請負生産では、伐採・搬出を請け負った山師が、それに従事する山子を調達しました。伐木・造材を担う山子と、運材を担う山子は区別されており、山子は山頭によって統率されていました。伐採・搬出は夏・冬ともに実施されましたが、夏は小羽(屋根葺き用の板材)や杉皮などを生産し、冬は角材や丸太などを生産しました。 伐採にあたり、米代川中・上流域では「番山繰」と呼ばれる輪伐法が実施されました。文化7年(1810)には、米代川中・上流域に男鹿山を加えた14か所の山林が番山繰の計画に組み込まれており、このほかに予備の山林が確保されていました。しかし、同年の時点では14か所のうち8か所は森林資源が枯渇し、長木沢も過半は伐採されていました。このため、翌8年以降には番山繰の計画立て直しが図られました。 また、文化期には森林資源の減少が問題となったため、森林資源の節約や、森林資源の回復を図る林政改革の一環として、部分林制度によるスギなどの植林奨励が進められました。ただし、スギが成木するまでには長期間を要するため、すぐには森林資源は回復せず、その利用は明治期(1868~1912)まで待たねばなりません。よって、幕末にかけて森林資源の減少は顕著となり、藩財政に占める材木生産の役割も小さくなっていったと考えられます。ただし、一方で文化期以降の藩は、自身の需要だけでなく、百姓の需要も認めて、彼らに対する有用樹種の払い下げの便宜を図っていった点も見逃せないでしょう。 〔芳賀和樹〕 参考文献 ▽岩崎直人『秋田杉林の成立並に更新に関する研究』(興林会、1939年) ▽秋田県編『秋田県史』第2巻近世編上(秋田県、1964年) ▽秋田県編『秋田県林業史』上巻(秋田県、1973 年) ▽能代木材産業史編集委員会編『能代木材産業史』(能代木材産業連合会、1979年) ▽脇野博『日本林業技術史の研究』(清文堂出版、2006年)
日本海に面し、冬に積雪の多かった秋田藩は、春になると土壌の養分が豊富に溶け込んだ大量の雪解け水に恵まれました。ただし、雪解け水を稲作などへ活用するためには、河川の上流の山林を適切に管理することが不可欠でした。もし、これらの山林が荒廃して水源涵養(すいげんかんよう)機能を充分に発揮できなければ、雪解け水は一気に河川へ流れ込み、場合によっては洪水となって田畑や屋敷を襲うからです。また、山林の水源涵養機能が低下すると、雪解け水だけでなく、降った雨水もすぐに流れ去ってしまい、日照りが続けば水不足に悩まされます。このため同藩では、特に農業用水の安定供給を目的にして、「水野目林」(みずのめばやし)と呼ばれる水源涵養林が保護・育成されました。 それでは、こうした水野目林は、実際にどのように管理されていたのでしょうか。この点を、仙北郡の入角山(いりすみやま)をとりあげて、具体的にみてみましょう。奥羽山脈の一部をなす入角山は、古くから横手盆地の野中村・八日市村・椿村(現・大仙市)の水野目林として重視されてきました。入角山を流れる入角川は、これらの村々にとって用水を確保するための貴重な水源であったのです。上記の村々は、のちに白岩前郷村(現・仙北市)を加えて、入角山の「水野目四ヶ村」と総称されました。 ここで、入角山の利用と保護・育成の歴史を、順を追ってみていきましょう。江戸時代初期の状況は具体的にはわかりませんが、少なくとも元和6年(1620)の時点で、水野目四ヶ村以外の村が入角山を伐り尽くした結果、水が不足し、水野目四ヶ村の水田は荒廃してしまいました。こうした状況を受けた藩は、承応4年(1655)に山林の伐採を制限し、水野目四ヶ村の村人も入角山の保護・育成に尽力するようになりました。たとえば、寛文元年(1661)に四ツ屋村(現・大仙市)の村人が銀200匁の上納と引き替えに入角山の伐採を藩に出願した際も、水野目四ヶ村は水源に支障が出るとの理由を藩に上申して反対し、不許可の裁定を得ています。 しかし、寛文8年(1668)~天和3年(1683)には、葛川村(現・大仙市)などによる薪の採取が、次々と許可されるようになりました。この結果、入角山は再び伐り尽くしとなり、水不足のために水田が日枯れしてしまう事態におちいりました。特に、宝永元年(1704)の旱魃では、水野目四ヶ村の水田が広範にわたって荒廃したといいます。さらに、正徳2年(1712)には入角川が氾濫し、周辺の水田が荒地となりました。入角山の水源涵養機能の低下は、極めて深刻な状況にあったのです。 そこで、正徳2年になると、水野目四ヶ村は藩に他村の利用を制限してもらうことで、水源涵養林を再度保護・育成しようとしました。これを受けた藩は、採草地を除いた3分の2を水野目林に指定して他村の利用を厳しく禁じ、残り3分の1を村々の入会地として認めました。その後は、水野目四ヶ村が水野目林の保護・育成に尽力したため、水源涵養機能は回復し、荒地も次第に復興させることができたといいます。 このように秋田藩領の村々は、森林の伐り尽くしと水不足を経験的に結びつけ、水源涵養林の保護・育成に尽力するようになったのです。 〔芳賀和樹〕 参考文献 ▽遠藤安太郎編『日本山林史』保護林篇上(日本山林史刊行会、1934年) ▽遠藤安太郎編『日本山林史』保護林篇資料(日本山林史刊行会、1936年) ▽遠藤安太郎編『山林史上より観たる東北文化之研究』(日本山林史研究会、1938年) ▽中仙町郷土史編さん委員会編『中仙町史』通史編(中仙町郷土史編さん委員会、1983年)
江戸時代の森林は、幕藩領主による材木生産や流通が盛んに行われていたイメージが強いですが、一方で土砂の流出を防いだり、渇水を防止する水源涵養の機能を担っており、領主や地域の人びとたちによって保護・育成されてきました。ここではその一つの事例として、熊本藩の植林事業の展開と、それに従事した御山支配役について見ていきたいと思います。 肥後国(熊本県)の大部分と豊後国(大分県)の一部を領有していた熊本藩は、寛永9年(1632)に細川忠利が入国してから明治4年(1871)の廃藩置県に至るまで、細川氏が統治していました。 細川氏が入国した後の熊本藩において、藩領内における山林の基本施策が定まったのは貞享元年(1684)のことでしたが、6代細川重賢による宝暦改革が行われた際に行政機構の再整備がなされました。この時、これまで設置されていた御山奉行が廃止となり、代わって設置されたのが御山支配役でした。この御山支配役を中心に、宝暦改革以後藩領内ではスギ・ヒノキの植林や天然生のマツの育成に力が入れられていきました。 こうした植林が熊本藩で盛んに行われていくようになる理由の一つに、水源涵養林の育成が挙げられます。熊本藩では、竹木材の他領移出が原則として禁じられていました。また、藩の主要産物である米穀は、肥後米として江戸や大坂で高い評価を得ていました。そのため、水源涵養機能を有する山林を育成することは、藩にとって重要なことだったといえるでしょう。 では、御山支配役たちはどのように植林事業を行っていったのでしょうか。ここでは熊本藩の御山支配役のなかでも、特に著名な木原才次という人物を中心に紹介していきます。 木原才次は享保18年(1733)に木原文次の嫡子として熊本で生まれました。享保20年、父とともに矢部へ移り住み、宝暦13年(1763)に御山支配役となりました。 才次は寛政5年(1793)から矢部にある大矢山への植林に着手しました。大矢山は麓に上益城郡の下名連石・御所・鶴ヶ田・川口の4か村(熊本県上益城郡山都町)があり、宝永~正徳期(1704~1716)にかけて乱伐と野火焼きが繰り返され、荒廃が進んでいました。そのため、水源は枯渇し、豪雨になったときには洪水の被害が麓の村々へおよぶといった事態も発生していました。当時の覚書によれば、「水源繁暢は、其の手永の見通し迄にてこれ無く、他郡に障り軽からぬこと」(遠藤安太郎編『日本山林史 保護林篇 資料』)とあり、大矢山が水源を育む存在としていかに重要であったかが窺えます。 才次は右のような状況を憂い、大矢山への植林を思い立ちます。当初、藩から許可が下りなかったため、才次は自ら試験的に三か所への植林を行いました。この植林が成功したことによって、才次は藩の許可を得て、寛政5年から文化6年(1809)まで大々的な植林事業を展開することとなります。 この植林事業は、1年につきスギ・ヒノキを10万本植樹し、それを10年かけて100万本植樹する計画がなされていました。植樹が目指された100万本のうち、75万本は藩から金銭が支給され、25万本は村の者たちの植林によって進められていきました。その結果、文化6年までに120万本の植林に成功しました。植林が成功した後、才次は御山支配役の職を辞し、同年4月7日に77歳で病没しました。 才次の植林事業は息子才九郎へと引き継がれ、以後天保期(1830~44)に至るまで大矢山への植林は続けられました。文化13年(1816)7月、藩は木原才次の功労を顕彰する目的で「大屋繁茂の記」という頌徳碑を駒返峠(熊本県阿蘇郡南阿蘇村)に建てました。碑文中には、木原才次がスギ・ヒノキの植栽にあたって「昼夜身力を尽くし、野火を制し諸木を伐り、檜・杉などの挿芽を致す」など、才次がこの植林事業に心身を注いだ様子や、死を迎える前に息子たちを呼んで、「此の山蕃栄の事に精力を尽くし、野火防禦の具に勤務を励すべし」と遺言を残したことなどが伝えられています(遠藤安太郎編『日本山林史 保護林篇 上』)。 このように、熊本藩の植林事業は御山支配役たちによって担われてきており、木原才次の他にも植林に従事した御山支配役の例が多く見られます。彼らは地域の様子や、そこで暮らす百姓たちの様子を直に感じることができたからこそ、水源を育む山の働きやその大切さを認識していたのかもしれません。 〔萱場真仁〕 参考文献 ▽遠藤安太郎編『日本山林史 保護林篇 上』(日本山林史刊行会、1934年) ▽森田誠一「肥後藩林政の性格について」(『熊本史学』5、1953年) ▽林野庁編『徳川時代に於ける林野制度の大要』(林野共済会、1954年) ▽塩谷勉「部分林制度の史的研究(4)」(『九州大学農学部演習林報告』25、1955年) ▽渡辺喜作『林野所有権の形成過程の研究―資料6 肥後細川藩林政史』(私家版、1984年)
日本では、強風や潮風、それによる飛砂などから暮らしを守る海岸林が、古くより保護・育成されてきたといわれています。ただし、中世以前はもともと存在した林を保護したものが多く、植林によって積極的に海岸林が造成されるようになるのは、江戸時代に入ってからのことでした。 たとえば、弘前藩の「潮風除林」、盛岡藩の「潮除林」、仙台藩の「潮霧須賀松」、水戸藩の「風潮林」、高知藩の「潮霧囲林」、鹿児島藩の「塩風除林」などは、潮風の防備を主な目的にして造成されたものです。以下では、特に日本海側で発展をみたと考えられる、海岸砂防林についてみていきましょう。 海岸砂防林が、各地で本格的に植栽されるようになるのは、主に17世紀後半以降のことです。この時期に各地で海岸砂防林が植栽されるようになった主な背景には、砂丘やその後背湿地における新田開発の進展がありました。江戸初期の新田開発は、河川氾濫を防ぎ、灌漑用水を確保することで、海岸から離れた平野部を対象に進められましたが、この時期には海岸に近い砂丘やその後背湿地が開発の対象となりました。そこで大きな障害になったのが、強風や潮風、それによる飛砂であったのです。そのため、各領主とも積極的に海岸砂防林を植栽させ、同時に極めて厳重な禁伐政策を採用しました。 ちなみに、その名称は地域ごとに様々で、弘前藩では「砂留並田方風除林」「砂留松仕立山」「屏風山」、幕領佐渡では「砂垣」、金沢藩では「砂込山」、鳥取藩では「砂除塩風囲」、福岡藩では「浜辺松」などと称されました。 海岸砂丘での植林に当たっては、まず、強風や飛砂を防ぐことが重要でした。そのため、植林前には垣が設置され、その風下に樹木が植栽されました。この垣は一般的にヨシの茎を編んで作られましたが、一列だけの地域や二重・三重に設けた地域もありました。また、木片で菰(こも)を固定し、風除けとする方法もありました。 こうした垣の設置には、単に苗木を強風や飛砂から守るためだけでなく、人工砂丘をつくって、植林場所の砂の移動を防ぐ目的もありました。すなわち、垣を設置すると、それが飛砂を受け止めて周囲に砂を堆積させ、いずれ垣が砂に埋没します。そうなったら、その上にさらに垣を設置して砂を堆積させ、これを何度も繰り返すことで人工的に小高い砂丘をつくり、その内陸側に植林をします。こうして人工的に砂丘をつくることで、植林場所に侵入する砂の量は大幅に減少します。 この方法が用いられた最も早い例としては、17世紀後半における松江藩の藩士大梶七兵衛の植林があげられます。このように、人工砂丘を造って内陸側に植林する方法は、幕末頃までには多くの地域で実施されるようになりました。 〔芳賀和樹〕 参考文献 ▽遠藤安太郎編『日本山林史 保護林篇 上』(日本山林史刊行会、1934年) ▽宮田長次郎編『郷土を創造せし人々(海岸砂防篇)』(大日本山林会、1934年) ▽立石友男『海岸砂丘の変貌』(大明堂、1989年) ▽小田隆則『海岸林をつくった人々』(北斗出版、2003年)
日本の山は、奥山と里山に大きく二分されます。奥山は人里を離れた奥深い山で、深山ともいわれます。一方の里山とは集落と接し、農民と生活をともにした山のことです。近年、自然の保全といったことを目的に、地域に密接した山林を「里山」と称して保護していこうとする動きが見られますが、江戸時代の里山とはどのようなものだったのでしょうか。 「里山」という言葉が最初に見られるのは、宝暦9年(1759)6月に作成された「木曽山雑話」(徳川林政史研究所所蔵)という尾張藩の史料であるといわれます。「里山」という言葉が登場するのは、木曽における山林の名称を解説した部分で、「御留山」「御巣山」「御留山・御巣山新囲」「明キ山」「草山」に続いて出てきます。 「木曽山雑話」は、寺町兵右衛門という尾張藩の上松材木役所に勤務した役人が著したものです。よって、この「里山」という言葉も藩の役人の立場から見て民家近くの山を指した造語であるといえます。当時の一般の農民たちが、家居周辺の山をみずから「里山」と称していたかについては定かではありません。しかし、彼らにとって「里山」はあまりにも生活に密着した存在だったので、日常的には単に「裏山」とか「草山」「柴山」などと呼ばれていたのではないかと思われます。 里山は水田稲作を行う農民にとって不可欠なものでした。青草や柴は刈敷という緑肥として、または堆肥として耕地に施していました。農家では一年中囲炉裏や竈の火を絶やさず、炊事をしたり、暖をとったりしましたが、こうした作業は農耕の肥料として重要な役割を果たす木灰の生産をすることも大きな目的の一つでした。里山から採取した枝や末木などといった梢の部分は、農民たちが薪にして自家消費したり、商品として現金稼ぎしたりしました。さらに、農民の家屋などを補修する建築用材や、刈り取った稲を乾燥させる稲架などに里山の立木が用いられました。 また、里山は食糧獲得の場でもありました。田畑では稲・麦・黍・稗・粟・大豆などの穀物を生産し、山では山菜などを採取し、自家消費したり、貢納物や商品としたりしました。 このように里山では、農民らによって下草・柴・落ち葉・樹木・幹などが伐採され、すべて運び出されてしまいます。そのため、次第に里山の土地はやせていきました。結果として、肥沃な土地を好む広葉樹が失われ、やせた土地でも生育するマツ類、とりわけアカマツ林が江戸時代の里山には生育していました。 アカマツは、農民にとって有用な樹木でした。薪・炭、農民の家屋などの建築用材、道・橋や開発新田や用水路に使う樋や杭などの土木用材に用いられました。また樹木の伐採後に残された根株には樹脂が多く含まれ、肥松と呼ばれ、松明として農民の夜なべ仕事や外出時の照明として利用されました。アカマツは、葉・枝・幹・根株とすべてが多様に利用され、農民たちにとって貴重な存在でした。 一方、このような農業利用の他に、工業利用もなされました。製鉄業・製塩業・窯業(焼物)などを行うには、継続的に大量な薪や炭が必要でした。江戸時代のこれらの産業は、里山の薪・炭をなくしては成り立たなかったといってよいでしょう。 〔栗原健一〕 参考文献 ▽有岡利幸『里山』Ⅰ・Ⅱ(法政大学出版局、2004年)
江戸時代の社会は、気候不順や自然災害などによって凶作となると、米価が高騰し、食料流通が滞るなどして、度々飢饉(ききん)に見舞われました。江戸時代の領主と領民の関係は、領民の百姓たちが年貢・諸役を上納するなどの負担をする一方で、領主は社会的な責務として百姓たちを「御救(おすくい)」して生業を保障するという相互依存の関係にあったといわれています。そのため、飢饉になると、百姓たちは領主に対して度々「御救」を要求しました。 その「御救」の方法の一つとして、飢饉の際の山間地域では「御救山(おすくいやま)」が設定されることがありました。「御救山」とは、風損・水害・火災などの災害や凶作などによる食料不足などから飢饉となった百姓たち(時には藩士・町人も)を救済するために、領主が山林を開放し、百姓たちがそれら山々から林産物を獲得して自家用に消費、あるいは商品化することによって生活の足しにしていた林政の一施策を指します。 ここでは、「御救山」が特に多く見られた東北諸藩を中心に、「御救山」の具体例を見ていきたいと思います。 まず弘前藩では、元禄期(1688~1704)・宝永期(1704~11)・享保期(1716~36)などに「御救山」の記録が確認できますが、「御救山」が最も多く見られたのは天明飢饉の時でした。特に天明3年(1783)8月の白神山地では、この時全面的に開山されたことが記録されています。また西之浜通(にしのはまどおり)(現青森県西津軽郡深浦町)では、村領すべての留山が村民に解放されましたが、藩は村々の被害状況などを勘案して杣入りの期間などを決定するなど、村によって異なる伐採方法がとられました。 盛岡藩では、宝暦の飢饉時に「御救明山」とマツ枝払いなどが許されました。この時は、村の近郊に位置する御山(おやま)からの伐採が許可されました。また、天明の飢饉に際しても、天明3年9月に「諸士在町」を救済するために「御救山」が設定されました。これは、城下近郊の松山を炊料として利用することを許可し、各町に対象の山を割り当て、薪の採集を許す形で実施されました。ところが、指定された「御救山」以外に勝手に入り込む者が現れたため、山林の取り締まりを強化するとともに、11月には「御救山」が追加されることになりました。結果、これら「御救山」は全領的範囲に広がり、合計209か山にまでおよんだのです。 仙台藩でも、「御救山」をめぐるいくつかの様相が明らかにされています。例えば、享保7年(1722)3月には、五串(いつくし)村(現岩手県一関市)などの村々から不作のため御林の払い下げが要求されました。藩は、金・穀物のほかに「御救」を供出することができず、困窮している者への救済は軽視できないため、村々からの願い出を許可しています。また天明4年閏正月には、高城村(宮城県宮城郡松島町)などの百姓に対して飢饉への「御救」として松島長老坂にある一里塚のスギの伐採が許され、寛政元年(1789)1月には、宮城新浜(しんはま)(現宮城県仙台市)の百姓に対して海岸林(御林)のマツ2547本が下されるなど、「御救」を目的とした多様な森林資源の利用が確認できます。 このように、「御救山」は百姓たちの危機に対する救済機能を果たしていたことは明らかですが、一方で問題もありました。 例えば弘前藩では、宝永4年(1707)に「御救山」が許されると、伐採の代償として御礼銭などが課せられ、資金的な余裕のない百姓たちは杣取りできないことがありました。こうした場合、藩は伐採権を商人に売却し、百姓らはその商人のもとで低額な労賃を得るに留まったのです。 また秋田藩領の出羽国秋田郡七日市(なぬかいち)村(現秋田県北秋田市)では、枝郷にある雑木林が度々「御救山」として許可され、その結果、天明3年の飢饉の翌年には柴山となってしまった事例も見られます。 江戸時代の人々は、飢饉の際に森林からの恵みを得ることで生きようとしてきました。このことからは、森林が人びとの生きるうえで最後の砦だったと言えるでしょう。その一方で、私たちは「御救山」として利用した後の森林のゆくえにも注視する必要があると思います。 〔栗原健一〕 参考文献 ▽遠藤安太郎『山林史上より観たる東北文化之研究』(日本山林史研究会、1938年) ▽小原伸『伊達仙台藩の林政』(宮城県水源林保護組合連合会、1954年) ▽農林省編『日本林制史資料』(臨川書店、1971年、初版は朝陽会、1931~34年) ▽鷹巣町史編纂委員会編『鷹巣町史 別巻 資料編2』(鷹巣町、1987年) ▽深谷克己『百姓成立』(塙書房、1993年) ▽菊池勇夫『飢饉の社会史』(校倉書房、1994年) ▽「新編弘前市史」編纂委員会編『新編弘前市史 通史編2(近世1)』(弘前市企画部企画課、2002年) ▽菊池勇夫『飢饉から読む近世社会』(校倉書房、2003年) ▽黒瀧秀久『弘前藩における山林制度と木材流通構造』(北方新社、2005年) ▽土谷紘子「天保飢饉時の弘前藩における山林利用」 (長谷川成一監修・浪川健治ほか編『地域ネットワークと社会変容』岩田書院、2008年) ▽金谷千亜紀「盛岡藩領五戸通における御山支配と山林利用」(『農業史研究』44、2010年) ▽長谷川成一『北の世界遺産白神山地の歴史学的研究』(清文堂出版、2014年)
閲覧日:
火曜日・水曜日10:00~16:30
*閲覧をご希望の場合は、事前に申請が必要です。
閲覧申請はこちら
*休日・祝日および、8/10~8/20、12/20~1/10、3/20~4/10は閲覧を休止します。