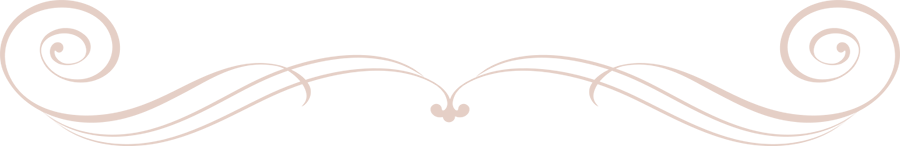
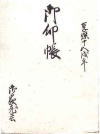
現存する尾張徳川家文書のなかに「御印帳」(「御家老共御印帳」)と題する小冊子が残されています。内容は、年ごとに村々から上納された三役銀(夫銀・堤.銀・伝馬銀)の一部を書き留めたものです。三役銀とは、一般的には村の石高に応じて課せられる税のことで、蔵入地(藩の直轄地)・知行地のいずれからも徴収されました。夫銀は、道路や橋・水路の普請などに、農民が年に三日の夫役に出ることになっていましたが、それでも不足した場合の人足を藩が雇う費用に充てました。堤銀は、木曽川の御囲堤など河川の堤防を建設・修復するための人足賃に充てたものです。また、伝馬銀は、藩領内の宿場において人馬を徴収する賃金に充て、のちに宿場への給付や貸し付けの資金にもなりました。 村々から上納された三役銀の一部は、「御印帳」に記載され、藩主の命をうけた重臣(年寄)によって秘密かつ厳重に管理されていました。これは、領民救済のための緊急用資金などにも捻出できるように、一般会計とは区別され、内密に確保されていたと推定されます。「御印帳」は享保15年(1730)2月分から記載が始まっており、6代継友・7代宗春・8代宗勝の時期までを書き留めた帳簿です。たとえば、享保16年7月には、夫銀・伝馬銀のうちから金46両3分・銀13匁9分5厘の上納があったことが記されています。 帳簿のなかには、使途不明のこの金銀の性格を知るうえで興味深い文言が記されています。まず、帳簿に記載されている金銀の使い道は、家老たちにも知らされておらず、「御隠密至極之儀」として藩主に一任されたと注記されています。
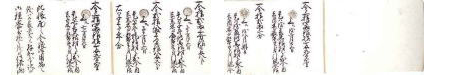
次に、上納された金銀は、この帳簿に重臣が記入捺印のうえ、直ちに藩主に差し上げ、お手許に置かれた「溜塗箱」に納めたとあります。また、「表御用金」(藩の財政)が不足したからといって、この金銀で補填するようなことはしてはいけない、領民を救済しなければならない時の手当を失うことにもなるからと、注意を促しています。そして最後に、この金銀が存在する趣旨を重臣たちは、強く心に留め置き、末永く後年まで伝えていくために、「御隠居様」の命により、この帳簿に注記したと記しているのです。 〔白根孝胤〕 参考文献 ▽「御印帳」(徳川林政史研究所所蔵)
藩主は一日をどのようにして過ごすのでしょうか。誰しも興味を引かれる事柄ですが、実は、大名の一日のスケジュールを詳細に復元するのは、非常に難しいものです。当たり前のように繰り返される日常生活は、かえって記録には残りにくいためだからです。そこで、ここでは藩主側近の職である御小納戸が記した「御小納戸日記」という史料を用いて、現在わかる範囲で殿様の暮らしぶりを覗いてみることにしましょう。 天保14年(1843)6月25日、参勤交代のため江戸を発した12代藩主徳川斉荘が名古屋城へと入城しました。これから再び江戸へ戻るまでの数か月間を、斉荘は国許の名古屋で暮らすことになります。 城中での殿様の私的な生活は、御殿の中の「奥」と呼ばれる空間で営まれました。一方、藩主としてのさまざまな執務は、「表」という空間で繰り広げられます。つまり藩主は、毎日「奥」から「表」へと“通勤”し、一日の執務が終わると再び「奥」へと戻っていく形をとるのです。
 定光寺源敬公廟焼香殿
(徳川林政史研究所所蔵)
定光寺源敬公廟焼香殿
(徳川林政史研究所所蔵)
藩主の起床時刻は、斉荘の場合、六半時(午前7時)でした。「尾州御小納戸日記」には「御目覚差定り候儀ニ付、日々不相認候」(お目覚めの時刻は決まっているので、これ以後は特に記載しない)とあるので、特に早起きする用事がない限り、起床時刻は決まっていたようです。 起床した斉荘は、「奥」において「御櫛」や「御膳」を済ませると、「表」へと出勤ます。「奥」と「表」とを隔てていた御錠口が開かれ、殿様の日常道具を入れたと思われる御挟箱が下げ渡されるとともに、斉荘が「表」へと現れます。これを「出御」といいました。出御の時刻は、おおむね四ツ時(午前10時)の場合が多いですが、その日に行われる行事によっては、これより早くなることもありました。 「表」に出た斉荘は、着替えを済ませると、まず「御祠堂」へと向かい、先祖の位牌に向かって焼香をしました。これは、一日における最初の行事で、毎日欠かさずに行われます。その後「例朝御目見」といって、側近役人たちと朝の挨拶を行います。「例朝御目見」には、時として御年寄(家老)衆が加わることもあり、このときには政務上の重要な令達などが藩主から発せられることもありました。 右のように毎朝の行事を済ませた後、藩主にはさまざまな仕事が待ち構えていました。その第一は家臣たちへの謁見です。月次御礼と呼ばれる謁見日には、家臣の格式に応じて殿中のさまざまな部屋で御目見を行いました。例えば、天保14年7月1日の「御小納戸日記」を見ると、最初に中御座之間で御年寄衆や御用列の面々と謁見を済ませ、そのまま焼火之間に回って御年寄列の人々および初出仕の家臣たちとの御目見を行い、続いて夜詰之間でその他の家臣たちの挨拶を受け、さらに水之間へと赴いて、別の初出仕の面々との御目見を済ませています。また、格式の低い家臣に対しては、部屋と部屋を行き来する途中で謁見を行っており、これは通りがかりに一瞥を加えるだけだったようです。こうした謁見の仕事は、月次御礼だけではなく、評定所式日には出座の者たちに対する御目見、さらには江戸へ赴く家臣や江戸から帰国した者との御目見など、実にさまざまな種類がありました。 殿様としての知識・教養を身につけることも欠かせません。藩主は、正月以外の毎月12日には、「月次講釈」といって夜詰之間で儒者から「論語」などの進講を受けることになっていました。また別の日には、桜之間で役者から「御仕舞御稽古」と呼ばれる能の稽古も受けています。 藩主として領内の事情を知っておくのも、殿様の重要な仕事です。同年8月4日の「御小納戸日記」を見ると、「御弐度目御膳」(昼食)を済ませた斉荘は、水之間奥締で木曽山の「刻形」(模型)を見ながら、役人から木曽の山々に貯えられている御囲材についての説明を受けています。 斉荘は、家臣たちの武芸などを好んで見物したようで、7月25日には奥向矢場御殿で槍術を、8月13日には同所で剣術を、閏9月16日には同じく矢場御殿で射術を、同月23日には奥向馬場御殿で乗馬を、同月26日には奥向矢場御殿において柔術を上覧しており、このほか御門前の馬場において奥向の者たちの乗馬を見るといったこともしばしば行われました。 また、武芸だけではなく、武具の管理の様子を視察することもありました。閏9月28日には、九ツ(正午)過ぎから城中の天守・小天守に渡り、そこからさらに御具足多門・御槍多門・御旗多門・東弓矢多門・西弓矢多門・大筒多門・御旗筒多門などをじっくりと巡覧、約3時間ほどをかけて入念に見分を行っています。
 名古屋城二之丸御殿
名古屋城二之丸御殿寺社などへ外出することもありました。先祖の命日に当たる日には、菩提寺の建中寺へ赴いて法要を営んでいる記述がしばしば見られるほか、閏9月7日には、初代藩主義直の廟所がある定光寺へと赴きました。ただし、このときは日帰りの参詣で、八ツ時(午前2時)に出発して四ツ時(午前10時)に定光寺へ到着、御廟に参詣したあと、着替えを済ませ昼食をとると、ただちに名古屋へ帰るという、せわしないものでした。
とりたてて用事がない日の藩主は、2~3日おきに江戸から送られてくる夫人や姫たちからの手紙を読んだり、新御殿で隠居生活をおくっている前大納言(10代藩主斉朝)からの書簡や、維学心院(9代藩主宗睦の娘維姫のことで、近衛基前に嫁したが、基前の没後に薙髪した)からの手紙を見るなどして過ごしていました。また、「延気」(気晴らし)と称して、下御庭(御下屋敷)へ出かけることもありました。7月25日は夕方より下御庭へと御成しており、8月11日には起床後ただちに下御庭へと向かっています。寝苦しい夏の夜のことでなので、いささかでも庭園で涼しさを求めようと、朝夕に出かけたのでしょうか。なお、8月11日の御成では五ツ時(午前8時)に帰御し、その直後に「御入湯」したとの記載がありますが、これが毎日定まったものであるのか否かについては判然としません。
一日の仕事が終わり、殿様が「奥」へ戻ることを「入御」と称していました。しかし、この時刻については、その日の行事のあり方などによって一定ではなかったようです。
〔太田尚宏〕
参考文献
▽「尾州御小納戸日記」
(徳川林政史研究所所蔵)
嘉永2年(1849)6月4日、尾張家に仕える家臣や領民たちが待ち望んでいた殿様が登場しました。その殿様の名は徳川慶勝といいます。慶勝は文政7年(1824)3月15日に尾張家の分家である美濃高須松平家の当主松平義建の二男として生まれました。幼名は秀之助と称し、義恕と名乗りました。尾張家を相続した際に「徳川」姓を与えられて徳川慶恕となり、のちに慶勝と改名しました。生母は水戸家第七代当主徳川治紀の娘規姫です。幼少の頃から読書を好み、武技も嗜む賢明な人物として高く評されていましたが、慶勝が尾張家当主となるまでにはかなりの月日を要しました。それは、慶勝が家督を相続する以前の尾張家は、艶福家として知られた11代将軍徳川家斉の息子や親族を押しつけられ、彼らが相次いで当主となっていたからです。こうした状況を打破して、慶勝が尾張家当主となるまでの長い道のりを探ってみることにしましょう
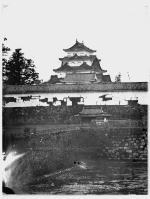 幕末・明治初年の名古屋城
幕末・明治初年の名古屋城将軍家斉の親族が尾張家当主となったきっかけは、9代当主宗睦の後継者問題が浮上したときでした。宗睦には治休・治興の2人の男子がいましたが、いずれも若くして死去したため、甥の治行を養子としました。しかし、治行も病死してしまいます。そこで今度は、寛政10年(1798)4月に将軍家斉の甥にあたる愷千代(御三卿一橋治国の長男)を養子としました。愷千代は、翌年9月に元服して将軍家斉から一字を賜り、斉朝と名乗りました。ようやく後継者が定まり安堵したのか、宗睦はその3か月後に死去しました。 宗睦の死後、家督を相続した斉朝にも子がいなかったため、文政5年(1822)6月に将軍家斉の子、斉温を養子としました。文政10年8月、斉朝の隠居により新たに当主となった斉温は1度も尾張に入国せず、藩政への関心も薄く、補佐役の付家老に依存する状況でした。そして、天保10年(1839)3月に斉温が21歳の若さで死去すると、幕府は将軍家斉の弟斉荘(御三卿田安斉匡の養子)を後継ぎとすることを申し渡しました。しかし、相次ぐ将軍家からの押し付け養子に対する不満が表面化し、家臣たちから斉荘の相続に強く反対する意見書が提出されました。この意見書には、 まず、斉荘の相続は、大御所家斉や12代将軍家慶の「思召」ではなく、老中水野忠邦と尾張家付家老成瀬正住の共同謀議によるものであること、尾張家が「東照宮之御血脈、公儀御分国」であることが軽視され、斉荘がいかなる明君なのか不明であることなど、幕府への不満と批判が綴られていました。続いて、「将軍家の子供を押し付けても家は治まらず、本来尾張家は諸大名の手本となるべき家柄であるから、このような大国の家督相続が横領簒奪されたような姿であっては乱世の基になるので、分家の慶勝が当主になるべきである」と主張しています。分家の美濃高須松平家は、尾張本家に世嗣がいない場合にしかるべき人物を本家に相続させる役割を果たしていたので、賢明な人物として評価の高かった慶勝に尾張家を相続してもらいたいという家臣たちの主張は筋が通っていると言えるでしょう。 ところが、この意見は、慶勝が尾張分家の出身といっても、初代義直(徳川家康九男)の直系ではなく、むしろ当時は水戸家との関係の方が近いとの理由で、幕府に退けられてしまいます(例えば慶勝と水戸家当主の徳川斉昭の子慶喜は従兄弟同士である)。さらに12代当主となった斉荘の死後、家督を相続したのは田安斉匡の子慶臧で、これで4代にわたって押し付け養子による当主が続く状況となりました。しかも、13代当主慶臧が14歳の若さで死去すると、幕府は斉荘の弟田安慶頼を当主にしようと画策しました。しかし、尾張藩内における反発がより一層強まったため、ついに幕府はこの相続を断念しました。こうして長い間家臣たちが待ち望んでいた慶勝の家督相続がようやく実現したのです。 当主なった慶勝は早速藩政改革に着手しますが、14代当主となって4年後の嘉永6年(1853)6月、国内を揺るがす衝撃的な出来事に直面しました。黒船の来航です。これを契機に時代が大きく動き出すなかで、慶勝は、弟の徳川茂徳(15代当主)・松平容保(会津藩主・京都守護職)・松平定敬(桑名藩主・京都所司代)とともに、激動の幕末を駆け抜けていくことになるのです。 〔白根孝胤〕 参考文献 ▽「文公紀事略」(徳川林政史研究所所蔵) ▽白根孝胤「尾張家における「両敬」の形成と将軍権威」(岸野俊彦編『尾張藩の総合研究』第四篇所収、2009年)
井伊直弼の専横政治に反発し、不興を買って隠居・幽閉させられていた14代藩主の徳川慶勝が、復権したのち、政治の表舞台に躍り出たのは第一次長州征討のときでした。 元治元年(1864)7月19日、京を追われた長州藩は、朝廷への嘆願を名目に、武力を伴って御所へ乱入しようと図りました。いわゆる禁門の変です。これを退けた朝廷は、幕府を通じて中国・四国・九州の21藩に対し、長州藩追討の命令を下しました。このとき出兵した諸藩を束ねる「総督」に命じられたのが徳川慶勝でした。
 徳川慶勝肖像写真
徳川慶勝肖像写真しかし、慶勝は当初、幕府による再三の総督就任要請に対して、言を左右にして容易に受諾しませんでした。総督受諾後の処置に関しても、実際に戦闘に至ることなく、薩摩藩の西郷隆盛らに長州藩への恭順工作を進めさせ、禁門の変の首謀者とされた家老3名の首級を差し出すなどの「寛厚之御処置」をとることで終結させたのです。このため、一橋慶喜から「(薩摩の)芋に酔ひ候」と皮肉られたように、慶勝の処置は、西郷らの進言を鵜呑みにしただけの弱腰で不十分なものとして映り、朝廷・幕府双方からの非難の的となりました。こうしたことから第一次征長における慶勝の対応は、やる気がなく、西郷らに踊らされたに過ぎないという評価が、現在に至るまで通説とされてきました。 しかし近年、こうした評価を覆し、慶勝の描いた征長構想を知り得る史料が発見されたのです。その史料とは、鳥取県立博物館所蔵の「贈従一位池田慶徳公御伝記稿本」です。これは、当時の鳥取藩主池田慶徳(徳川慶勝とは従兄弟にあたる)の事蹟をまとめたもので、その中に収録された在京藩士の書簡などから、第一次征長をめぐって「総督」慶勝が何を考え、どのように終結させようとしていたかが、手に取るようにわかります。 これによると慶勝は、幕府からの総督就任要請を病気を理由にして固辞しながら、征長をめぐる京都の議論が「御和談」となり、武力行使を回避する方向に向かうことを期待していたと記されています。つまり慶勝は、やる気がなかったわけではなく、京都の動きを横目ににらみながら、長州をめぐる議論が穏便な形で収まることを期待して、時間稼ぎをしていたのです。しかし、会津藩などの強硬派の主張が受け入れられ、軍事動員が避けられない情勢となるにおよんで、慶勝は総督就任を受諾する代わりに、征長に関する全権委任を要求することとなります。そして元治元年10月4日、慶勝は将軍家茂から黒印の軍事委任状を発給され、正式に征長総督を受諾しました。 しかも、総督になった慶勝の背後には、従兄弟で関白の二条斉敬がいました。鳥取藩の京都留守居役が国許の側近役へ送った10月10日付の書状には、二条が尾張藩家老の成瀬正肥に対して、三家老切腹をはじめとする長州問題の解決策を「御内々御咄し」した結果、慶勝もそれに沿った「御内意」で事を進めるだろうといった記述が見られます。慶勝は、関白の二条斉敬と気脈を通じながら、長州処分のプランを固めていったのです。 慶勝は、京都から大坂へと陣を進め、征長参加諸藩の重臣を招集して「大坂軍議」と呼ばれる会合を設け、軍令状の交付、征長方針の伝達を行いました。しかし慶勝は、実は軍議そのものには大きな期待をしていませんでした。むしろ軍議の開催を口実にして征長諸藩の藩主大坂に集め、そこでの「御密議」を通じて「寛厚之御処置」に関する意見の集約を図ろうとしたのでした。池田慶徳が実弟の浜田藩主松平武聡に送った10月17日付の書簡には「密策之上ニ於て之策略謀計も種々御坐候事故、其辺被尽御評議度」として、岡山・鳥取・福岡・広島・徳島・高松などの藩主に上坂を促したといいます。さらに慶勝は、岡山藩主の池田茂政を介して水戸出身者と思われる人物らを雇い入れ、徳島・広島・福岡の三藩に対して「御誘引」の使者を送り周旋するなど、「寛厚之御処置」の実現に向けた動きを進めていったのです。 しかし諸大名の意見集約は、結局、大坂軍議までには間に合わず、慶勝はそのまま広島へと赴くことになります。しかし「寛厚之御処置」を貫き、それを朝廷・幕府を納得させるためには、諸大名の意見一致が不可欠と考えていた慶勝は、一部の反対論を押し切って「広島軍議」と呼ばれる会合を開催、ついに「寛厚之御処置」を「衆議」としてとりまとめることに成功しました。 諸藩の解兵を進めたのち、京へ向かった慶勝は、松平容保や一橋慶喜に対して征長参加大名の京都招集を提案し、「衆議の帰する所を朝廷に奏上し、然る上施行せられ」るよう強く要望しました。慶勝が描いた征長構想の最終段階は、諸大名の「衆議」を朝廷に直接働きかけるというものだったのです。しかし、慶勝のこの考えは、松平容保らの強硬な反対にあって、ついに実現をみませんでした。落胆した慶勝は、所労を理由に名古屋へと退き、みずから政治の舞台から降りてしまったのです。 〔上野 恵・太田尚宏〕 参考文献 ▽『贈従一位池田慶徳公御伝記』(鳥取県立博物館、1988年) ▽岩下哲典『幕末日本の情報活動』(雄山閣出版、2003年) ▽上野恵「第一次長州征討における総督徳川慶勝の構想とその対応」(『昭和女子大学文化史研究』第11号、2007年)
尾張15代藩主徳川茂徳の事績を知る人はそう多くはないでしょう。安政5年(1858)に藩主となるも、前藩主慶勝の藩政を望む勢力から忌避され、文久3年(1863)に隠退、慶勝の実子元千代(義宜)にその座を譲りました。6歳の元千代には慶勝が後見となり藩政を運営したので、茂徳は中継ぎ藩主のようなものでした。しかし、ひとたび藩を越えて中央政局に目を転じてみると、政治的に重要な位置を占めていた茂徳の姿が浮かび上がってきます。
 徳川茂徳肖像写真
徳川茂徳肖像写真例えば、「徳川家恩顧之臣」が、慶応2年(1866)9月10日付で紀州家留守居に宛てた投書を見てみましょう。この投書は、当時の中央政界で大きな影響力を誇っていた一橋慶喜を、連枝・家門・譜代・旗本を糾合して大挙誅殺すべきだとした檄文でした。時はまさに、幕末の徳川幕府を揺るがし、その権威を失墜させた長州戦争が、14代将軍家茂の死をもって8月21日に停止され、翌月2日に休戦協定が結ばれた直後でした。 投書によれば、慶喜は、兼ねてから自己の栄達を望み、将軍職に就き兵馬の大権を掌握しようと目論んでいたといいます。それゆえ13代将軍家定を毒殺させ、その跡を継いだ家茂にも牙を向けました。慶喜は自らの威名を天下に示すため長州討伐を主張し、家茂を欺き大坂まで呼び寄せましたが、対長州交渉を長引かせ、家茂の苦悶を誘因したといいます。その結果、心労が祟って家茂は死去。まさに刃を用いずして家茂を追いつめ、ついには死に至らしめた元凶として慶喜は糾弾されているのです。 もっともここで書かれた内容に、全く信憑性はありません。しかし、当時の幕府内(特に江戸)で、慶喜がいかなる立場にあったかを知る上で、興味深い内容となっています。「恩顧之臣」は慶喜を抹殺し、その首を日光東照宮に奉納することで尊霊を慰め、徳川家の威信を復活させようと企図していました。ここで注目したいのは、慶喜追討の旗頭として「尾張前大納言源同(玄同)公」が据えられていることです。玄同とは、隠退した茂徳が用いた号でした。なぜ茂徳が慶喜討伐の中心と期待されたのか、その原因を探るには、時間軸をもう少し前に戻さなければなりません。 慶応元年5月16日、将軍家茂は長州再征のため江戸を進発し、閏5月25日に大坂城に入りました。その家茂のもとには、慶喜はじめ茂徳の姿もあったのです。第一次長州戦争における処分を批判された徳川慶勝に代わって、親幕府的な立場の茂徳に幕府から従軍命令が下ったためでした。しかし、茂徳は翌2年正月に江戸留守役に任命されて江戸に下向、中央政局から一歩後退することとなります。ただし、この下向が、御三卿清水家を継承する意味を込めたものであったことは、留意すべき点だと思います。 実は茂徳は、国内外の政治的諸問題で苦境に立った家茂を補佐したことから、家茂から「父親」のように尊敬されていた人物でした。家茂の実父斉順(11代紀州藩主・家斉七男)は、かつて清水家の当主をつとめており、それゆえ清水家は家茂にとって特別な家であったといえます。この当主に茂徳を据えることは、双方の親子関係を具体化する措置と位置づけられるでしょう。 清水家継承者とされた茂徳は、家茂死後の政争において大きな役割を果たしました。「徳川家恩顧之臣」が、慶喜追討の頭目と仰いだのは先に見たとおりです。徳川家へ忠誠を果たそうとする彼らは、家茂から尊敬・信頼され、慶喜と同様の御三卿当主とされた茂徳に、その対抗馬としての期待を寄せたわけです。事実、茂徳は、慶喜や田安亀之助らとともに、家茂の後継者の一人としてその名を連ねていたのでした。 〔藤田英昭〕 参考文献 ▽藤田英昭「慶応元年前後における徳川玄同の政治的位置」(『日本歴史』658号、2003年)
明治11年(1878)9月3日、尾張徳川家当主の徳川慶勝は、午前10時過ぎに本所相吉町の自邸を人力車で出立し、銀座二丁目10番地の二見朝隈写真館に出向きました。 この写真館には、慶勝の弟にあたる徳川茂栄(茂徳・一橋徳川家当主)、松平容保(会津松平家隠居)、松平定敬(桑名松平家隠居)も集まり、4人揃って写真撮影に臨みました。掲載の写真は、この時撮影されたものです。
 右から慶勝・茂栄・容保・定敬
右から慶勝・茂栄・容保・定敬4人を撮影した写真師二見朝隈は、慶勝の跡を継いだ徳川義禮やその邸宅などを撮影しているので、尾張徳川家御用達の写真師の一人であったと考えられます。嘉永5年(1852)、長野神林に生まれ、夜間の写真撮影に成功し写真雑誌の刊行などに貢献した北庭筑波に写真術を学び、明治8年に日本橋三丁目に写真館を開業しました。銀座店は、4人を撮影する1か月前、8月初旬に開業したばかりでした。 慶勝ら4人は、尾張藩の分家高須松平家に生まれた実の兄弟です。かつて対立と協調を繰り返しながら、それぞれ異なった立場で幕末史を歩んできたのでした。 長男慶勝は、嘉永2年(1849)に本家尾張藩を相続し、叔父の水戸斉昭にならった藩政改革を断行するも、安政5年(1858)の政争に敗れ、斉昭とともに大老井伊直弼により隠居・謹慎に処せられました。その後、次男茂徳が尾張藩主に就任、茂徳は付家老竹腰正諟の指導のもと、田宮如雲ら慶勝の側近藩士を一掃し、井伊大老に追随する藩政を敷きました。文久2年(1862)に慶勝が藩政に復帰すると、前藩主慶勝を推戴する勢力と、藩主茂徳を押す勢力とが対立し、藩政の混乱は中央政局を巻き込み加速度的に進行しました。その結果、茂徳は尾張藩を出て御三卿一橋家を相続、ついで慶応3年の青松葉事件の悲劇を招来するに至ります。青松葉事件によって処刑された渡辺新左衛門や武野新右衛門らは、まさに茂徳を推戴する中心人物だったのです。多くの犠牲を払って尾張藩は「勤王」へと藩論を統一し、戊辰戦争では周辺諸藩への「勤王誘引」を展開するなど新政府軍の一翼を担っていくのです。 一方、会津藩主となった三男容保は、文久2年(1862)に京都守護職に就任し、過激尊攘派が跋扈する京洛の治安維持に奔走、さらには朝幕融和を実現するため14代将軍徳川家茂を長期に滞京させようと周旋を繰り広げました。このとき慶勝も入京し、ともに朝幕融和の運動にあたっています。京都からほど遠い東国の会津藩主が朝廷工作をする上では、近衛家と縁戚関係を持ち、従二位大納言という格式を誇った兄慶勝が大いに頼りになったことはいうまでもありません。桑名藩主となった四男定敬も、元治元年(1864)4月に京都所司代となり、容保と協力して朝幕融和や長州問題に関わるなど、中央政界で活躍していきました。 大政奉還・王政復古といった時局の変転に反発した容保・定敬兄弟は、鳥羽・伏見において薩長両藩に決戦を挑むも敗走し、朝敵の汚名を着せられました。その彼らの助命嘆願に奔走したのが、一橋家当主となっていた茂徳(茂栄)その人でした。新政府に従った慶勝も表立った行動はできないものの、茂徳を陰ながら支援し、決して兄弟たちを見捨てることはありませんでした。しかし、長州藩の強硬姿勢などで結局は許されず、会津若松城の籠城戦や五稜郭陥落を経て戊辰戦争は終結、容保は鳥取藩に、定敬は尾張藩に御預の身となりました。2人の謹慎が解除されるのは、明治5年を待たねばなりませんでした。 激動の幕末をそれぞれの立場で生き抜いた高須四兄弟。彼らは何を思ってカメラの前に立っているのでしょうか。それは4人にしか解らないことなのかもしれません。 〔藤田英昭〕 参考文献 ▽「御記録第一六六号 日記」(徳川林政史研究所所蔵) ▽『徳川将軍家と会津松平家』(福島県立博物館、2006年)
北海道開拓に始まる徳川農場の歴史を振り返るとき、見逃してはならないのが、農場直轄であった山林事業の役割です。特に大正期(1912~26)には、農場全体の収入に占める山林事業収入の割合が高くなり、その収益が農場における様々な活動の原動力になっていったと考えられます。 そもそも尾張徳川家が、北海道で山林事業に積極的に取り組むようになったのは、明治21年(1888)に、政府の七重勧業試験場に附属していた大野養蚕場(のちの大野農場)を取得してからのことでした。取得当初こそ、毎年の植栽樹種や本数は一定ではありませんでしたが、同33年以降には、スギとカラマツを中心に毎年一定の本数を植栽するようになり、渡島半島という地域に適した森林経営技術の確立が窺われます。 こうした明治期における植林の展開に支えられ、大正期には徳川農場の山林事業が本格化していきます。その大きな契機が、次の2つの出来事でした。1つ目は、大正3年における第一次世界大戦の勃発です。大戦による好景気によって木材価格が高騰すると、翌4年には大野農場で間伐を積極的に実施し、大きな利益を獲得しました。 2つ目は、大正12年9月1日に発生した関東大震災です。死者は約9万人、行方不明者は約1万人、重軽傷者は約5万人を数え、建物の被害は全焼約38万世帯、全壊約8万世帯、半壊約9万世帯に昇った未曾有の大災害に際し、徳川農場は震災復興用材として大量の材木を販売しています。 ここで注目したいのは、大正15年における徳川農場の概況報告書です。次の一節には、当時の尾張徳川家当主であり、徳川林政史研究室(のちの当研究所)の創立者でもあった農場主の徳川義親と、その指示を受けた農場スタッフたちの、山林事業に対する想いが込められています。
最近ニ於ケル主侯ノ御意見ニ徴スルモ、将来造林ニ意ヲ傾注シ、荒廃セントスル地、又ハ他ニ使用ノ途少ナキ地ヲ利用セサルヘカラス 世運ノ進展ニ伴ヒ、必然的到来スヘキ木材問題、薪炭材・用材ノ欠乏ニ対応スヘキ国家的重大対策ナルハ、疑ヲ入レサルトコロナリ (大正15年「事業概況報告書綴」、徳川林政史研究所所蔵)
すなわち、徳川義親と農場スタッフたちは、山林事業を徳川農場の利益を図る産業としてのみ考えるのではなく、むしろ広い視野から、「将来」到来するであろう薪炭材や用材の不足という「国家的課題」に対応するための重大問題であると強く認識し、造林を図ったのでした。この認識の背景には、大正12年に発生した関東大震災の経験があったものと思われます。
 徳川農場のカラマツとスギ
徳川農場のカラマツとスギこの主張に基づき、2年後の昭和3年(1928)には、徳川林政史研究室の林学士であった川合徳太郎により、大野農場における森林経営の計画を示した「施業案」が編成され、より計画的で合理的な森林経営が志向されるようになります。 以上のように、明治期以来、多くの人びとの手によって営まれてきた山林事業は、現在八雲産業株式会社へと受け継がれています。 〔芳賀和樹〕 参考文献 ▽「大野事業区経営案」(徳川林政史研究所所蔵) ▽林善茂「徳川農場発達史(1)(2)(3)」(北海道大学『経済学研究』5・6・13号、1953~57年) ▽榎勇「北海道に於ける小作制農場の変質過程」(『北海道農業研究』13号、1957年) ▽八雲町史編さん委員会編『改訂 八雲町史 上巻』(八雲町役場、1984年)
尾張徳川家第19代当主徳川義親は、先々代の17代慶勝が開拓に着手した北海道八雲の地を幾度となく訪れています。目的のひとつは「熊狩」を行うためでした。 八雲の徳川農場では、義親の熊狩のために部隊を設けて万全の体制で行われました。これは当時の新聞をも賑わせ、義親は「熊狩の殿様」と異名をとるほど話題になりました。 その義親と八雲との関係で見過ごせないもののひとつに、「熊彫」があります。木彫りの熊は、現在も北海道の工芸品として有名ですが、この木彫り熊は実は八雲で生み出されたものだったのです。木彫り熊の完成には、徳川義親と徳川農場、そして八雲の住民が大きくかかわっていました。 大正9年(1920)、日本全国の農村は、恐慌の影響や若者の都市流出のために逼迫しており、具体的な改善策が求められていました。当時貴族院議員であった義親は、その現状を打開すべく農村改革の必要を訴えていました。折しも、義親はこの頃欧州各地へ旅行し、スイスの農村で木彫りの熊を目にします。これを見た義親は、農閑期の副業として、木彫りの製作を推奨しようと思いついたのです。 帰国した義親は、八雲へ木彫り製品を持ち込み、徳川農場長の大島鍛を中心に木彫りの実践を薦めました。八雲の住民は、当初あまり積極的ではなかったようですが、まずは徳川農場の主導で木彫品の製作を進めることになりました。早速その成果を発表する場として、第一回農村美術工芸品評会が開催されます。これは、木彫品に限定せず、さまざまな作品の出品を認めていたこともあって、1000点以上もの作品が集まりました。 こうした動きは各地の新聞でも取りあげられ、八雲では本格的に農村美術運動が展開し、「農村美術研究会」が開催されました。徳川農場によって運営されたこの研究会では、木の彫り方や染色方法、材木の選別など技術の向上が目指されるとともに、農村美術という概念の捉え方についても意見交換が行われました。 数年後、八雲に根付いた農村美術運動は、いよいよさらなる発展を求められるようになりました。昭和2年(1927)には、八雲の木彫り熊が展覧会で入賞し、秩父宮へ献上されるといった機会を得るようになっていました。そこで、大島鍛は以下のような趣意書を作成します。
愈作品ノ種類ヲ纏メ、土産品トシテ之ニヨリ、大八雲ヲ天下ニ紹介センノ機ガ到来致シマシタ 八雲ノ土産品、何ガ最モ廣ク八雲ヲ紹介シ、且ツ雄辯ニ八雲ヲ物語ツテクレルデセウ ソレニツキ、八雲ノ成リ立チヲ解剖シテ考ヘマシテ、八雲開祖ノ徳川侯ノ熱烈ナル主唱ト絶大ナル誘掖ニヨツテ、今将ニ生レ出デントスル郷土藝術品ハ、侯爵ノ有名ナ熊狩ニ因ミ「熊彫」トナスコトガ最モ意味深長、且ツ侯爵ニ對スル今日アル報謝ノ微意ナリト相談ハ、研究會員方ノ間ニ一決(中略) ソシテ、来ル八月ニハ八雲開墾五十周年記念祭を機トシ、左記規定ニヨリ展覧會ヲ開催シテ、八雲ノ熊彫を大々的ニ発表シ、販路開拓ノ第一歩ヲ雄々シク踏ミ出サント計畫致シマシタ (「八雲開墾五十周年記念熊彫展覧会開催趣意書」、徳川林政史研究所所蔵)
この史料は、八雲開墾50周年にあたる昭和3年に出された熊彫展覧会の開催趣意書です。ここで注目すべきは、なぜ八雲の土産品・郷土芸術品として「熊彫」が選ばれたのか、そしてなぜ「熊彫」という名が付けられたのか、この趣意書からわかることです。 この史料から、木彫り熊を選んだのは、八雲開祖の「徳川家」の主唱で行われたためで、「熊彫」の命名については、その発起人である義親の有名な「熊狩」に因んだことがわかります。最たる理由としては「侯爵ニ對スル今日アル報謝ノ微意ナリ」と記されているように、八雲住民から徳川家への感謝の念が込められたものでした。徳川家は、八雲開拓後も積極的にインフラ整備を進め、八雲の発展に寄与していたことが知られていますが、八雲の人々にとっては徳川家が特別な存在であったことがうかがわれます。徳川家と八雲の人々との関係を如実に示すものが「熊彫」であり、その「熊彫」が八雲の郷土芸術品となった意義は大きいといえるでしょう。 こうして、初の熊彫展覧会は盛況のうちに終わり、以後土産品として流通するよう、熊彫の生産性の向上と販路の構築が図られていきます。昭和6年頃から本格的に販売が開始されていきました。熊彫は、道内の観光名所や百貨店のほか、東京、あるいは長野の軽井沢などでも販売され、全国的にも有名な土産品となったのです。 この流れに便乗し、八雲だけでなく道内各地で木彫りの熊が生産されました。八雲は熊彫ブランドを守るために商標登録し、八雲ならではのオリジナルの熊を生産し続けていきました。その後、第二次世界大戦の影響を受けて苦しい時代を経験しますが、現在は北海道の工芸品として、その伝統が受け継がれているのです。 〔根岸美季〕 参考文献 ▽徳川義親『私の履歴書』(日本経済新聞社、1964年) ▽徳川義親『最後の殿様』(講談社、1973年) ▽大石勇『伝統工芸の創世 北海道八雲町の「熊彫」と徳川義親』(吉川弘文館、1994年) ▽太田尚宏「徳川義親の熊狩と八雲『熊彫』の誕生」(財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構『アイヌ-美を求める心』、2010年) ▽藤田英昭「大正・昭和初期における徳川農場の理念と実践」(徳川林政史研究所『研究紀要』第47号、2013年)
閲覧日:
火曜日・水曜日10:00~16:30
*閲覧をご希望の場合は、事前に申請が必要です。
閲覧申請はこちら
*休日・祝日および、8/10~8/20、12/20~1/10、3/20~4/10は閲覧を休止します。